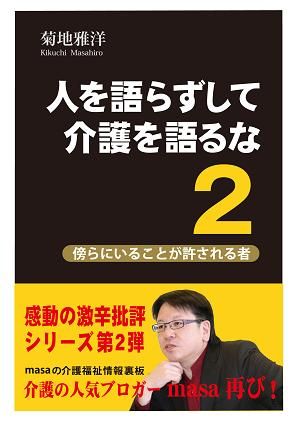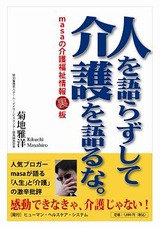高齢者福祉サービスの分野では、施設、居宅サービスに関わらず、個別ケアが求められ、集団的ケアは「前時代的で品質が低いサービス」とされている。それはその通りであろう。
しかし人の発達過程において集団経験は非常に重要で、欠くことができない。
周りを見渡すと社会や他者とうまく接することができない若者が増えているように思う。介護実習を行う学生にも、少なからず知識の欠如でない部分で、この仕事に向かないと判断せざる得ない状態の人がいる。それらの人々の生活暦はどうなっているのだろうと疑問を持つことがしばしばあり、特に親子関係が異常な状態(30を超えた大人が親から自立していなかったり、親もそれを自覚していなかったり)という状況に接すると、成長過程でどのような社会との接触が行われてきたのか、考え込んでしまうことがある。
今日は日頃の内容と少し違った角度であるが、人の発達に影響する集団力について考えてみたい。
人は、生まれながらの遺伝的なものだけに基づいて人間としての発達を遂げることはほとんどあり得ない。遺伝的素質とともに、社会生活環境における学習を通して「人間」に創り上げられていくのである。
我々が社会にふさわしい一員として作り上げられていく過程を「社会化」と呼ぶ。
人は通常、まず家族という基本的な集団に生まれ、育てられていく。どんな人も始めは自らの生命の維持も安全も、全て周りの大人に依存する状態であり、1対1の密接な関係から、人間に対する基本的信頼感情を育てていく。
しかし幼児期の非常に早い段階で、人は既に周囲の大人ばかりではなく、自分と同じような仲間との交流を求めるようになり、2歳児は平行的な「遊び」を展開する中で「友達」を意識し、3〜5歳と進むにつれ家族から遊び仲間へと経験の輪を広げ、学童期になると、仲間に受け入れられるか否かは、その子供にとって次第に決定的要因となり始め、大人の支配や保護の及ばぬ子供独自の領域が作り上げられる。
このように子供は家庭、学校、地域社会の中で様々な集団に属し、人間同士の交わりを通し人間性や社会性を獲得していく。親の過度な溺愛は、この部分の発達過程を阻害する場合がある。
学童幼児期は、子供達の集団に、従うべき規律と守るべき秘密があり、大人に依存はしているが大人の干渉は嫌ってくる。そして思春期に入ると自我を確立し、大人になるための既存の価値観や権威と対立する様々な葛藤を経験するが、その不安定な時期を支えるのが仲間との同一視であり、集団の中に安定を求めつつ、やがて社会人として責任を持つようになる。
だからこの時期の引きこもりはその後の発達に重大な関係構築能力に障害をもたらす。ネット社会がもたらす負の遺産も無視できないが、何より、家庭における親の関わり方や役割が重要な問題となってくる。
成人期には、自分の家庭や職場での交わりが大きな比重を占めるが、地域社会への参加や、能力・興味に基づく任意の集団参加を通し社会的役割を果たしながら、人間としての自己能力を伸ばし、人に依存したり、されたりするような体験から情緒的ニーズを満たしていく。
つまり自立だけが重要ではないのだ。人に頼ることができる、その方法を獲得することも成長の一つの過程である。
老年期には、家族構成も変わり、職場も持たなくなったりして、新たな集団参加が必要になる。この点が成人期と異なるが、仲間の持つ意味合いは成人期と変わらず、高齢者であっても、社会において活動的であり、学習し、創造的な活動を行うことは意味がある。その欲求を満たす集団は高齢期でも必要なのだ。
集団処遇は否定されても、集団自体の効用は認めるべきで、施設サービスや集団で利用する通所サービスなどの居宅サービスでは、この集団力を良い方向に個人と接合させる視点が求められてくる。
だから福祉援助の専門家には集団論の理解が不可欠である。
ただし、一言断わっておくが、特養など高齢者施設の生活を「集団生活」というくくりで捉えている人々がいるが、それは大きな間違いで、それら高齢者施設は単なる「共同生活の場」に過ぎず、集団生活を理由にした制限ルールや権利侵害は許されるものではない。
ここは治療を目的とした「入院」などとは違うところである。
介護・福祉情報掲示板(表板)
しかし人の発達過程において集団経験は非常に重要で、欠くことができない。
周りを見渡すと社会や他者とうまく接することができない若者が増えているように思う。介護実習を行う学生にも、少なからず知識の欠如でない部分で、この仕事に向かないと判断せざる得ない状態の人がいる。それらの人々の生活暦はどうなっているのだろうと疑問を持つことがしばしばあり、特に親子関係が異常な状態(30を超えた大人が親から自立していなかったり、親もそれを自覚していなかったり)という状況に接すると、成長過程でどのような社会との接触が行われてきたのか、考え込んでしまうことがある。
今日は日頃の内容と少し違った角度であるが、人の発達に影響する集団力について考えてみたい。
人は、生まれながらの遺伝的なものだけに基づいて人間としての発達を遂げることはほとんどあり得ない。遺伝的素質とともに、社会生活環境における学習を通して「人間」に創り上げられていくのである。
我々が社会にふさわしい一員として作り上げられていく過程を「社会化」と呼ぶ。
人は通常、まず家族という基本的な集団に生まれ、育てられていく。どんな人も始めは自らの生命の維持も安全も、全て周りの大人に依存する状態であり、1対1の密接な関係から、人間に対する基本的信頼感情を育てていく。
しかし幼児期の非常に早い段階で、人は既に周囲の大人ばかりではなく、自分と同じような仲間との交流を求めるようになり、2歳児は平行的な「遊び」を展開する中で「友達」を意識し、3〜5歳と進むにつれ家族から遊び仲間へと経験の輪を広げ、学童期になると、仲間に受け入れられるか否かは、その子供にとって次第に決定的要因となり始め、大人の支配や保護の及ばぬ子供独自の領域が作り上げられる。
このように子供は家庭、学校、地域社会の中で様々な集団に属し、人間同士の交わりを通し人間性や社会性を獲得していく。親の過度な溺愛は、この部分の発達過程を阻害する場合がある。
学童幼児期は、子供達の集団に、従うべき規律と守るべき秘密があり、大人に依存はしているが大人の干渉は嫌ってくる。そして思春期に入ると自我を確立し、大人になるための既存の価値観や権威と対立する様々な葛藤を経験するが、その不安定な時期を支えるのが仲間との同一視であり、集団の中に安定を求めつつ、やがて社会人として責任を持つようになる。
だからこの時期の引きこもりはその後の発達に重大な関係構築能力に障害をもたらす。ネット社会がもたらす負の遺産も無視できないが、何より、家庭における親の関わり方や役割が重要な問題となってくる。
成人期には、自分の家庭や職場での交わりが大きな比重を占めるが、地域社会への参加や、能力・興味に基づく任意の集団参加を通し社会的役割を果たしながら、人間としての自己能力を伸ばし、人に依存したり、されたりするような体験から情緒的ニーズを満たしていく。
つまり自立だけが重要ではないのだ。人に頼ることができる、その方法を獲得することも成長の一つの過程である。
老年期には、家族構成も変わり、職場も持たなくなったりして、新たな集団参加が必要になる。この点が成人期と異なるが、仲間の持つ意味合いは成人期と変わらず、高齢者であっても、社会において活動的であり、学習し、創造的な活動を行うことは意味がある。その欲求を満たす集団は高齢期でも必要なのだ。
集団処遇は否定されても、集団自体の効用は認めるべきで、施設サービスや集団で利用する通所サービスなどの居宅サービスでは、この集団力を良い方向に個人と接合させる視点が求められてくる。
だから福祉援助の専門家には集団論の理解が不可欠である。
ただし、一言断わっておくが、特養など高齢者施設の生活を「集団生活」というくくりで捉えている人々がいるが、それは大きな間違いで、それら高齢者施設は単なる「共同生活の場」に過ぎず、集団生活を理由にした制限ルールや権利侵害は許されるものではない。
ここは治療を目的とした「入院」などとは違うところである。
介護・福祉情報掲示板(表板)
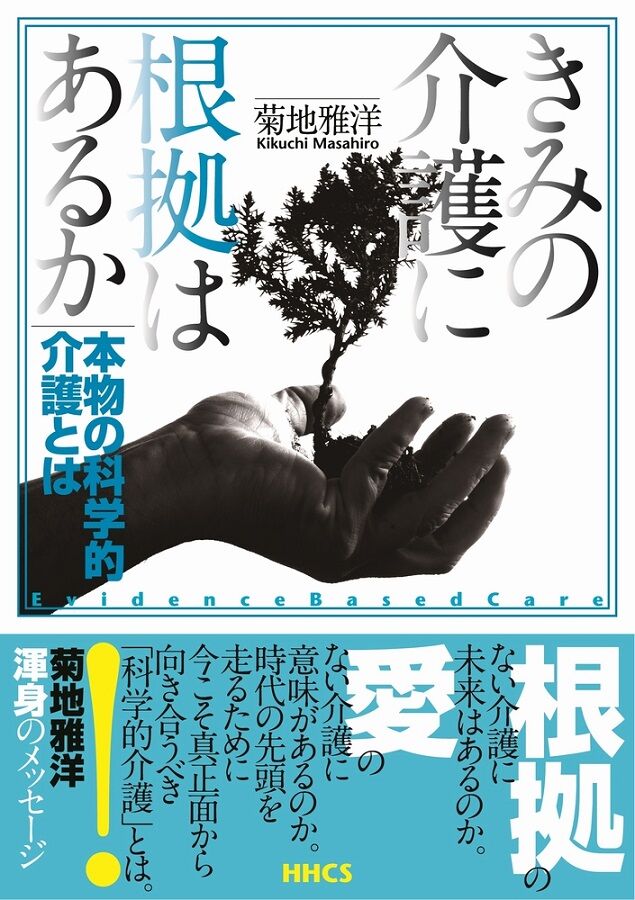
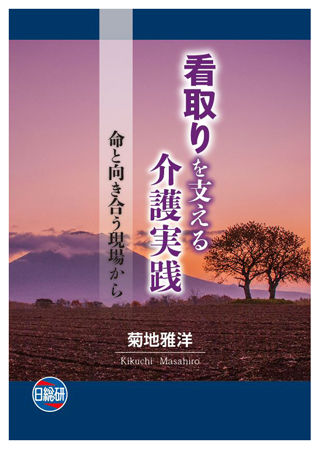

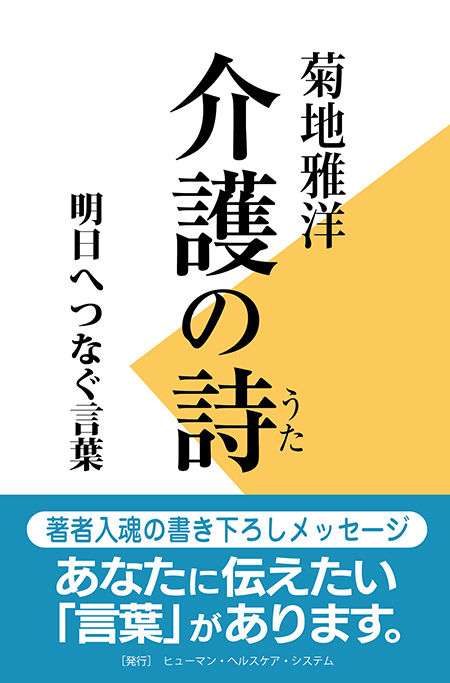
 感動の完結編。
感動の完結編。