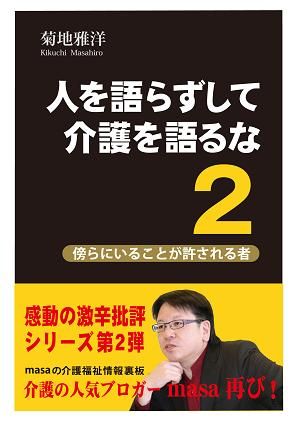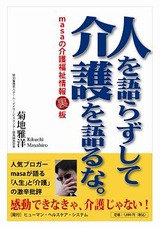現役の介護支援専門員の方々の中に、将来ケアマネジメント業務は、「AIによるケアプラン自動作成」にとってかわられるのではないかと懸念する人がいる。
しかしそんな心配はないと言い切っておこう。
現行で国が推奨しているケアプラン作成ソフトは、実際にはケアプランを自動作成するものではなく、ケアプラン作成支援ソフトでしかない。作成担当者にヒントを与えるために第2表を例示するに過ぎないのである。
しかもその内容たるや首をかしげるものも多く、このソフト作成担当者と、それを推奨する国の担当者が、いかにケアマネジメント実務からかけ離れたところで、AIをいじくっているに過ぎないことがよくわかる。
所詮、官僚とかSEといった介護の専門家ではない素人がいじくりまわしているに過ぎないのだ。対人援助のプロたる者が恐れるに足る相手ではない。
それが改善されて、将来的にケアプランが本当に自動作成されたとしても、それだけではケアマネジメントは完結しない。
ケアプランは単に、利用者の暮らしの維持・改善に有効な社会資源をつなぐためのツールに過ぎないのだから、ケアプラン自動作成ソフトが介護支援専門員のケアマネジメントに替わることは不可能なのである。
ケアマネジメントの本質は利用者に社会資源をつなぐ過程で、揺れ動く利用者の感情に寄り添って、その時点で必要な精神的支援を図りつつ、感情の揺れや、その感情の根本となっている思いにしっかり対応することである。機械にはそれは不可能である。
逆に言えば、介護支援専門員がその資格に胡坐をかいて、単なるケアプランナーに陥り、利用者の感情に寄り添いながら、利用者と様々な社会資源をつなぐという仕事をさぼっていたとしたら、感情がなく不快な思いをさせない機会によるケアプラン作成の方がましだと言われかねなくなる。
そうならないように、利用者の暮らしぶりが良くなったと、利用者本人が自覚できるケアマネジメントに努めてほしい。
大事なことは、ケアプランを作成することをケアマネジメントと思い込まないことと、自分の抽出した生活課題の解決目標が達せられておりさえすれば、ケアマネジメントはうまくいっていると勘違いしないことだ。
感情ある人の暮らしに寄り添って支援する職業では、何より利用者本人の満足度が重要なのだ。ケアマネジャーが良かれと思う結果が出たとしても、それに利用者が満足できなければ成功とはいえないのである。
「それが良い暮らしというのです。」なんていう価値観の押し付けほど、利用者にとって鬱陶しいものはないのである。
ケアマネジメントは、利用者に最もふさわしい社会資源をつなげる仕事である。
その過程では、私たちの思いを利用者につなげて、利用者の感情を私たちの感性につなげる必要がある必要がある仕事なのである。
この過程を怠けてはならない。この過程を大切にしなければならないのである。「繋げるが命」と呪文のように唱えて、日々の実務に当たるべき仕事がケアマネジメントなのである。

雪解けの大地に可憐な花を咲かせる、「さくらそう」のように、誰かのあかい花になるために、「繋げるケアマネジメント」を忘れないでほしい。
主役はあくまで利用者自身である。ケアマネジャーはわき役になる必要もない。わき役はケアマネジャーがつなげる誰かであっても良いのだ。
私たちは表舞台の陰で、黒子に徹する役割を果たすだけでよいのだ。
私たちの影さえ見えない状態で、利用者の笑顔が前面にあふれているケアマネジメントが、一番優れた方法論といえるのかもしれない。
※登録から仕事の紹介、入職後のアフターフォローまで無料でサポート・厚労省許可の安心転職支援はこちらから。
北海道介護福祉道場あかい花から介護・福祉情報掲示板(表板)に入ってください。
・「介護の誇り」は、こちらから送料無料で購入できます。
・masaの看取り介護指南本「看取りを支える介護実践〜命と向き合う現場から」(2019年1/20刊行)はこちらから送料無料で購入できます。
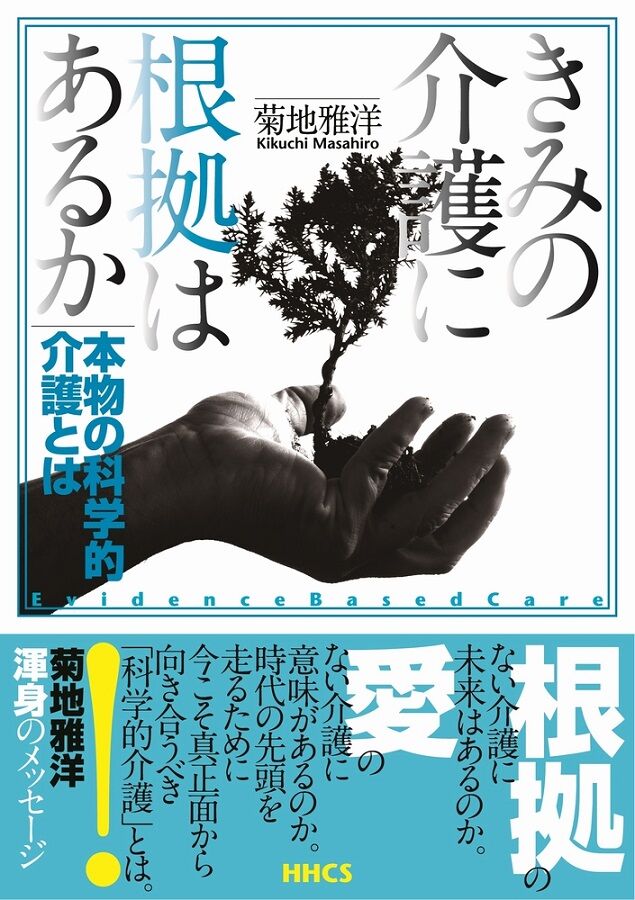
新刊「きみの介護に根拠はあるか〜本物の科学的介護とは」(2021年10月10日発売)をAmazonから取り寄せる方は、こちらをクリックしてください。
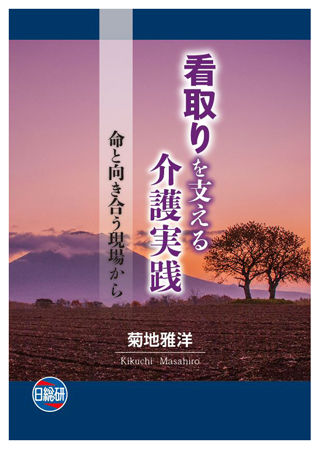

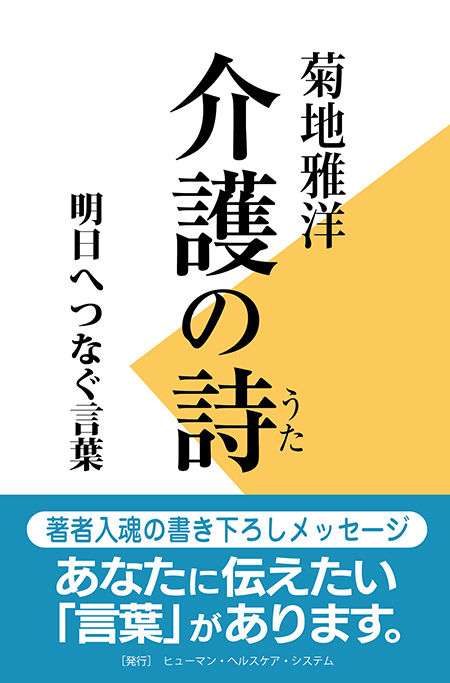
 感動の完結編。
感動の完結編。