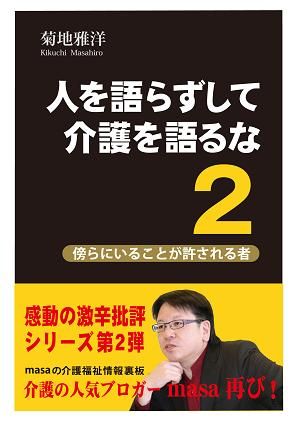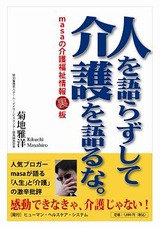12/5に開催された、『第104回社会保障審議会介護保険部会』に提出された資料、介護保険制度の見直しに関する意見(案)の28頁は、「2.給付と負担(全体に P)」という見出しが書かれているだけで、内容は空白のままである。
つまりそこに書くべき国民負担増について、会議までに調整がつかずに、内容を書くことができなかったという意味だ。
ここに書かれる予定だった内容とは、具体的には2割負担者の拡大を行うのか、行うとすれば後期高齢者医療制度並みに年金+その他の所得合計が200万円以上まで範囲を広げられるのかという問題である。
居宅介護支援費の自己負担化や、要介護1と2の対象者の、「訪問・通所介護」の地域支援事業化という国民負担増と給付抑制策が見送られることが確実となった次期制度改正において、利用者の2割負担をスタンダードにするための、対象者拡大は岸田首相も実現を強く望んでいた対策であり、年内に何としても結論を出したかった改正案でもある。
しかしその調整が困難を極めた背景には、物価高が及ぼす政治的影響という背景もある。諸物価が高騰する中でその対策が無策ではないかという批判がある中、内閣の支持率が下げ止まらないことから、このままでは来年4月の統一地方選挙を戦えないという危機感が政府与党にはある。
よって今の時期に国民負担増は強引に推し進められないという声が与党の有力議員を中心に広がっていることが大きく影響している。

そのため12/7に行われた、「全世代型社会保障構築会議」で公表された素案11頁では、この問題について次のように記している。
介護保険の持続可能性の確保
今後、更なる介護ニーズの増加が見込まれる中、介護保険制度の持続可能性を確保するため、「骨太の方針 2022」や「新経済・財政再生計画 改革工程表 2021」等に掲げられた課題について、来年の「骨太の方針」に向けて検討を進めるべきである。
このように、「給付と負担の見直し」については、年内に結論を出すことをあきらめたとうことだ。
しかも、「来年の「骨太の方針」に向けて検討」とうことであれば、最長骨太方針(経済財政運営と改革の基本方針)が示される時期まで、結論が先送りされる可能性があるという意味だ。
骨太の方針は、毎年6月頃に出されているので、2割負担者の拡大の結論もそこまで引っ張られる可能性があるというわけである。その時期だと統一地方選挙も終わっており、次の選挙も近直にはないので、国民負担増もしやすいということであろう。なんとも姑息な対応である・・・。
また素案10頁には、「介護現場の生産性向上と働く環境の改善」として、「生産性向上に向けた処遇改善加算の見直し」が記されている。
何気なく見逃してしまいそうな箇所であるが、次期報酬改定に向けて、3種類に分かれてますます複雑化した処遇改善加算の見直しが明記されているという意味は大きい。
これによって、処遇改善加算の一本化や基本報酬への組み入れなどが議論の俎上に乗せられる可能性が高くなる。
ただし処遇改善の更なる拡充とは一言も書かれていないために、単に加算体系を単純化して、そこに手当てする予算は増やさずに、配分の事業者裁量を拡充してお茶を濁す結果に終わらないとも限らない。
そうしないためのアクションがこれから関係者に求められてくる。その覚悟を持たねばならない。
※登録から仕事の紹介、入職後のアフターフォローまで無料でサポート・厚労省許可の安心転職支援はこちらから。
北海道介護福祉道場あかい花から介護・福祉情報掲示板(表板)に入ってください。
・「介護の誇り」は、こちらから送料無料で購入できます。
・masaの看取り介護指南本「看取りを支える介護実践〜命と向き合う現場から」(2019年1/20刊行)はこちらから送料無料で購入できます。
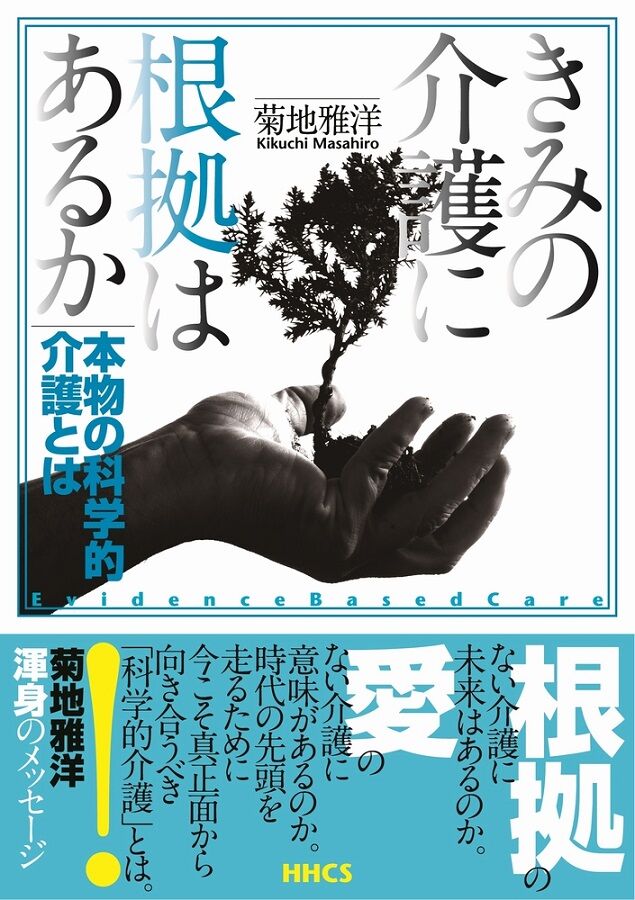
新刊「きみの介護に根拠はあるか〜本物の科学的介護とは」(2021年10月10日発売)をAmazonから取り寄せる方は、こちらをクリックしてください。
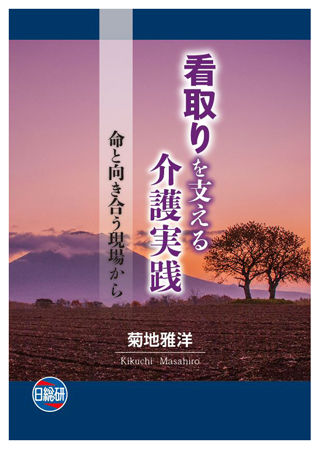

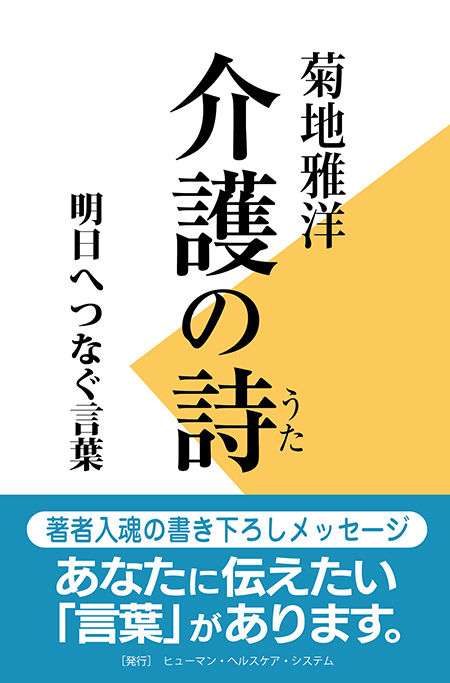
 感動の完結編。
感動の完結編。