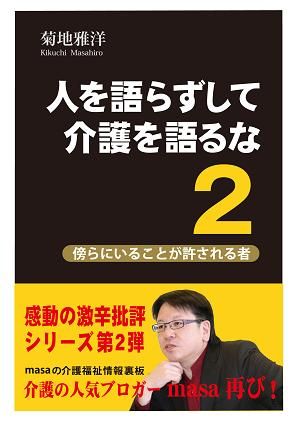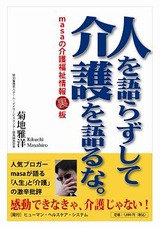9月15日に更新した、「軽介護者の訪問介護と通所介護はどうなるのか」で指摘したように、次期制度改正(2024年度〜)では、軽介護者(要介護1と2)の訪問・通所介護の総合事業化はないのではないかと僕は予測している。
僕と同意見だという人はたくさんおられると思う。
この件に関して26日に開催された社保審・介護保険部会で議論が沸騰した。
軽介護者の訪問・通所介護の総合事業化に賛成の意見を述べたのは、日本経団連の代表委員のみで、「重度者への支援に給付を重点化していくべき」・「軽度者へのサービスをより効率的な形に変えるべき」という給付抑制に偏った考え方を示している。
これに対し認知症家族の会代表委員は、「要介護1、2の人に軽度者とレッテルをはれば、サービスを減らせるかのような、非常に粗雑な審議は絶対に避けて欲しい。介護保険料を支払い、サービスが必要と認定されても在宅で暮らすことができない人をこれ以上増やさないで欲しい。過重な介護負担に起因する高齢者虐待、介護心中、介護殺人などの悲劇をこれ以上増やさないで欲しい」と述べた。
市民委員の面目躍如たる国民目線の意見である。こうした国民の声を国はしっかり受け止めてほしい。

また全国老施協の小泉委員は、「要介護1、2の高齢者に専門性の乏しいケアで対応することになり、自立支援のケアを劣化させる」・「地域の実情に合わせた多様な人材・資源を活用したサービスを提供できる、という見通しは実態を無視した空論であり、現実的ではない」・「総合事業へ移行すれば、在宅ケアの質・量を確実に低下させ、長年築いてきた在宅ケアは著しく後退してしまう。過去の積み上げを破壊し、先人たちの努力を踏みにじる改革であり、断固として反対」と堂々たる正論を述べている。
まさに介護の場の声を代表するプロの意見である。心より拍手を送りたい。小泉さん!あんたは偉い!!
こうした総合事業化への厳しい批判が国に届くことを願っている。
ただ26日の議論も、厚労省が総合事業化案を必要な改正案として示したわけではなく、制度の持続可能性を担保するため、財務省などがこの案の実現を要求していることを厚労省が説明したことが議論の発端になっている。
そういう意味では、厚労省が総合事業化に積極的な姿勢を取っているわけではないと思う。2024年度からの訪問・通所介護が総合事業化され、介護給付から外されるという大きな変革はされないのではないだろうか。
しかし確実に総合事業化は見送られると言い切れない要素もある。
例えば28日には政府の、「全世代型社会保障構築会議」が行われている。この会議は今後の社会保障制度改革の方向性を有識者らと話し合うものだが、そこで介護分野では、現役世代にかかる負担が重くなり過ぎることを避ける視点にも配慮して、「高齢者の負担能力に応じた負担、公平性を踏まえた給付内容のあり方」を検討していく方針が明示されている。
「公平性を踏まえた給付内容のあり方を検討する」という意味は、軽介護者のサービスを見直し、介護給付は重介護者に重点化するという意味で、訪問・通所介護の要介護1と2の対象者の総合事業化は、当然その視野に入ってくる。
政府がこの考え方を強力に推し進めた場合、厚労省は腰砕けになるやもしれず、 経過措置期間を設けたうえで、2024年度〜随時軽介護者の訪問・通所介護を総合事業化する可能性はゼロではない。
どちらにしても中長期で考えれば軽度者改革の議論が進んでいく可能性は十分あり得る。それは誰も否定できない。
仮にもしそうなった場合、通所介護事業者の生き残る道はあるのだろうか。そのことも考えておかねばならない。
しかし今日は時間切れである。明日そのことは改めて論ずることにしようと思う。明日の記事は、「もし軽介護者の通所介護が総合事業化されたとしたら・・・。」にしようと思う。明日のお昼ごろに読みに来てほしい。
なお本日朝5時、CBニュースの僕の連載記事がアップされた。そちらもぜひ参照願いたい。
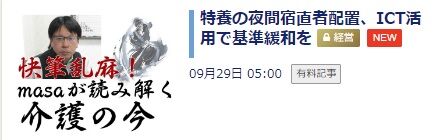
(※もし軽介護者の通所介護が総合事業化されたとしたら・・・。に続く)
※登録から仕事の紹介、入職後のアフターフォローまで無料でサポート・厚労省許可の安心転職支援はこちらから。
北海道介護福祉道場あかい花から介護・福祉情報掲示板(表板)に入ってください。
・「介護の誇り」は、こちらから送料無料で購入できます。
・masaの看取り介護指南本「看取りを支える介護実践〜命と向き合う現場から」(2019年1/20刊行)はこちらから送料無料で購入できます。
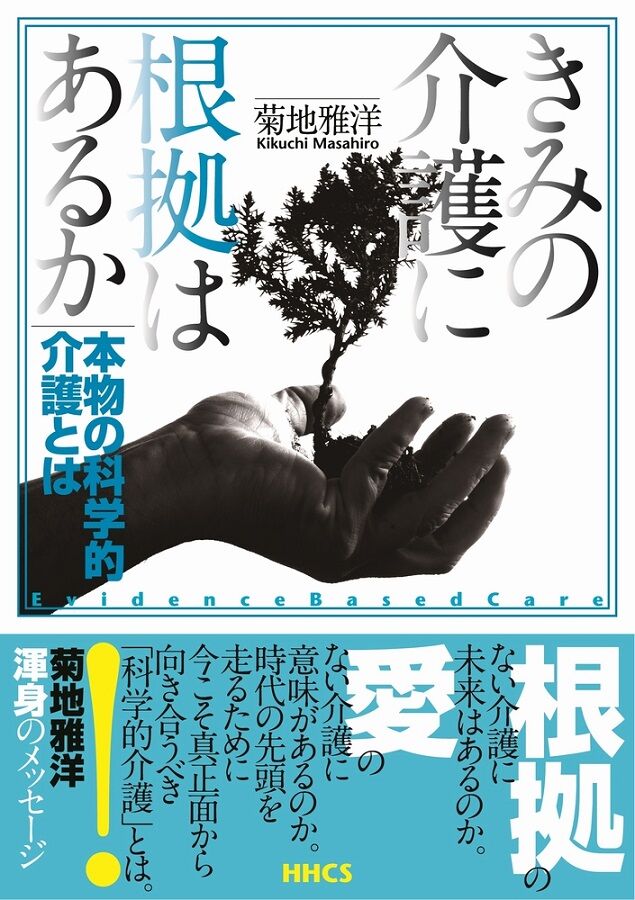
新刊「きみの介護に根拠はあるか〜本物の科学的介護とは」(2021年10月10日発売)をAmazonから取り寄せる方は、こちらをクリックしてください。
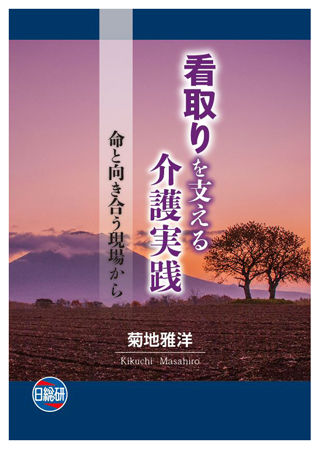

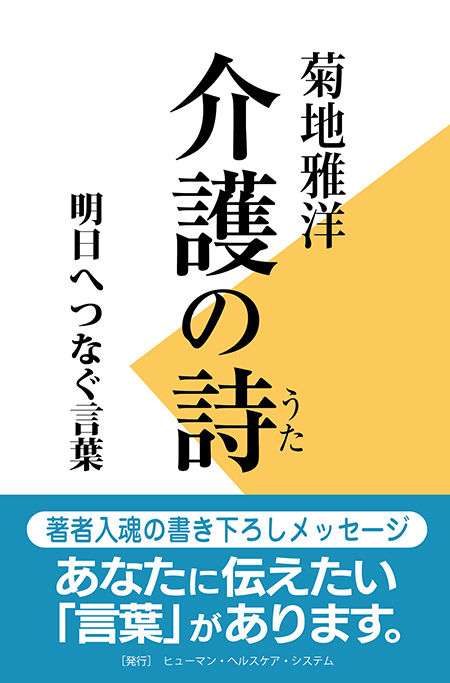
 感動の完結編。
感動の完結編。