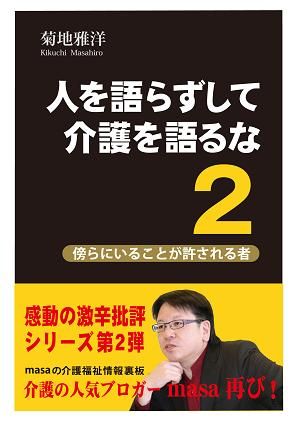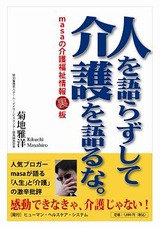介護サービス利用者の方々は、介護事業者にとって大切なお客様である・・・この論理を否定する人は、介護という仕事を通じて、対価(給料)を得てはならない。
ボランティアとして関わるなら別であるが、介護という行為で給与を得ている以上、介護サービスを利用する人はすべてお客様なのである。その理屈は誰も否定できない。
介護の仕事もサービス業であり、お客様に対して失礼のないように接することは、ごく当たり前の社会常識である。丁寧な言葉遣いや丁寧な態度を、「よそよそしい」とか、「親しまれない」という理屈で否定する人は単なるおバカさんである。
そもそも、「よそよそしくならないようにフレンドリーに接するため」という理屈で、顧客対応する人の言葉遣いが、「ため口」であるというおかしな状態になぜ気が付かないのだろう。
広辞苑でも何でもよいから、「ため口」という言葉の意味を辞書で引いて確認してみろと言いたい。
ため口とは、「目上の者が目下の者に対して使う言葉」であって、それはお客様を含め、目上の人に使うべき言葉ではないし、その言葉遣いが親しみやすさを表すこともないのである。
ため口の正しい意味を知っている人にとっては、ため口対応される状態とは、「人を馬鹿にした言葉遣い」で対応されているという意味でしかなく、失礼極まりない態度と映り、憤っているのだ。
それは決して顧客対応として許されてよい問題ではない。
こうした社会常識のない人が、たくさん介護を職業としているからこそ、介護事業におけるため口対応がなくならないのである。恥ずべきことである。
ところで今現在、巷では新型コロナウイルスのオミクロン株が爆発的に広がって、一時面会制限を緩めていた介護施設等でも、再び面会制限や外出制限が厳重に行われるようになっている。
世界的パンデミックという現在の状況を考えると、それはやむを得ないことであるといってよいとは思う。
しかし対人援助という仕事の、本来の目的は、人の尊厳と権利を護る仕事であることを決して忘れずに、制限をすることが私たちの権限であるという誤解をしないでほしい。
社会状況を鑑みてやむを得ず制限を行う場合であっても、その制限はできるだけ緩やかにできないかと知恵を絞る人が、「対人援助者」でなければならない。制限を当たり前と思わず、申し訳なく思う人が対人援助者でなければならないのである。
面会・外出制限で、ますます密室化する介護施設・居住系サービスは、外部の人の目が届きにくくなってくる。外部の人の声も入ってくなくなる。第3者の冷静な評価も届きにくくなっているのが現在の状態である。
だからこそなお一層のこと己を律して、利用者の方々の尊厳と権利を護る目を曇らせないようにしてほしい。
外部の人の目と耳が届かないからといって、職員の対応が乱暴になっていないかを確認してほしい。状況がどのように変わろうと、利用者の暮らしと心を護ることに変わりはなく、サービスマナーはその基盤となるのである。
コロナ対応下で介護従事者は、「社会機能維持者」(エッセンシャルワーカー)であるとして、濃厚接触者との待機期間が短縮されている。このことをご存じな方が多いだろう。
しかしそれは同時に、エッセンシャルワーカーとしての使命や責任を果たす必要があるとい意味でもある。

その使命と責任を果たすべき人たちに、人権意識やサービスマナーの視点が欠けてしまえば、それは絵に描いた餅どころの騒ぎではなく、単なる「詐欺」であると言われても仕方がないと思う。
だからこそどうか言葉を正しく使いこなす人になってほしい。そして人に愛を届けるエッセンシャルワーカーとしての責任を果たしてほしい。そう切に願うのである・・・。
※登録から仕事の紹介、入職後のアフターフォローまで無料でサポート・厚労省許可の安心転職支援はこちらから。
北海道介護福祉道場あかい花から介護・福祉情報掲示板(表板)に入ってください。
・「介護の誇り」は、こちらから送料無料で購入できます。
・masaの看取り介護指南本「看取りを支える介護実践〜命と向き合う現場から」(2019年1/20刊行)はこちらから送料無料で購入できます。
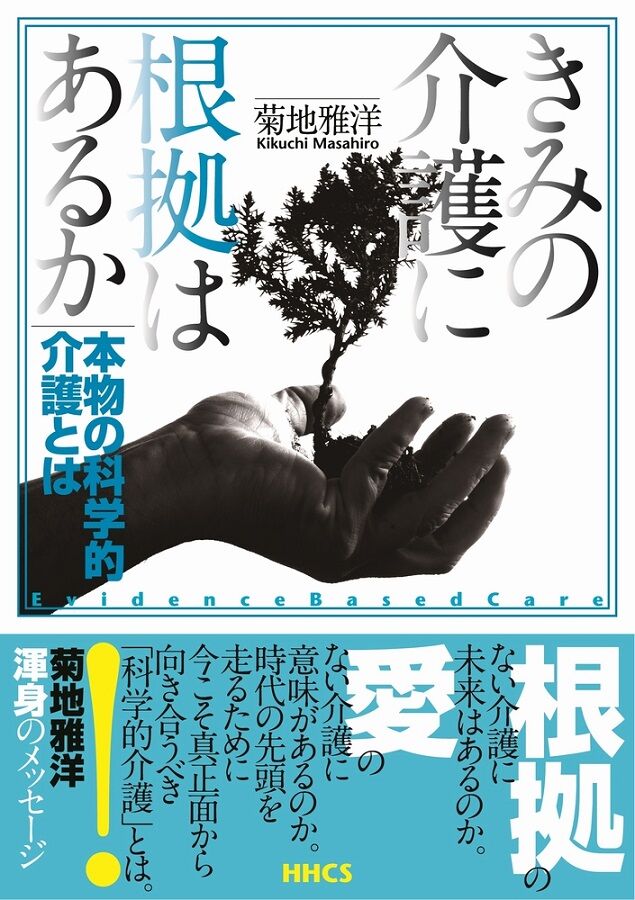
新刊「きみの介護に根拠はあるか〜本物の科学的介護とは」(2021年10月10日発売)をAmazonから取り寄せる方は、こちらをクリックしてください。
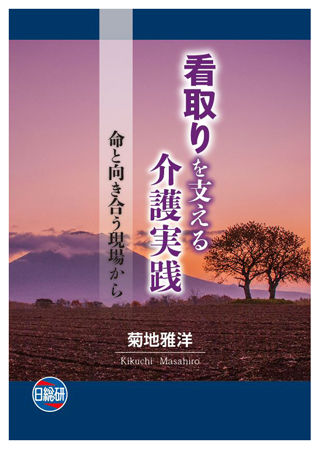

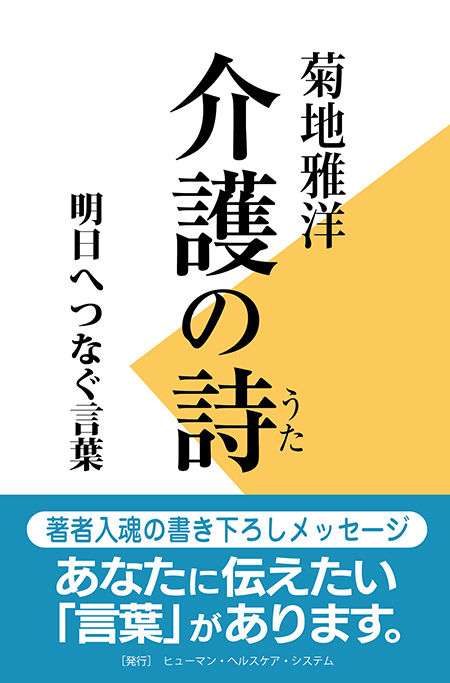
 感動の完結編。
感動の完結編。