昨日は秋葉原のスタジオで、オンラインセミナー介護人材確保策全4回分のうち、第1回分の生配信と、9/16(水)19:00〜配信予定の2回目分の録画を行った。
今日は一旦北海道の自宅に帰るが、このあと10/6(火)に3回目の生配信と、11月に4回目の録画配信を行う予定になっている。このオンラインセミナーの案内は、こちらのサイトで随時更新掲載されていく予定なので注目していただきたい。(※今日現在は9月の配信予定分まで掲載されています。)
参加予定者は180名以上であったが、実際にオンラインにつなげてくださった人数は130人を少し超えた人数とのことであった。参加申し込みをされた方は、昨日聴き逃しても後日録画配信分を視聴できるため、都合がつかなかった50人以上の方々は、そちらを視聴されるのだろうと思う。
昨日のオンライン講演はユーチューブでの生配信であったので、僕の講演が終わった直後からリアルタイムでチャットを利用した質疑応答も行った。
その中で、「内定者が就職する前に断るケースが増えているが、どう思うか」という質問が出された。
内定辞退理由が、面接試験等で示された企業理念や条件等を再考して自分の考えや希望にマッチしないということであるなら、それは採用面接の目的の一つを達成しているという意味なので特に問題ないと思う。むしろ不満や疑問を抱えながら、とりあえず働いてみようと考える人が、一旦働いて仕事を教えている途中に、「やっぱ無理です」と辞められるよりずっとマシだと思う。やる気のない人に手をかける無駄が省けるからである。
しかし内定辞退者が以前にも増して増えているとしたら、その辞退理由は別にあって、そのことは職員募集している事業者にとって深刻な問題を示している可能性がある。
特に事業者側が面接で、その人材に手ごたえを感じて、是非就職してもらいたいと思うような人材が内定を辞退するケースが増えているのなら、理由は別にあると考えたほうが良いだろう。
仕事ができる有能な人材ほど就職や転職に際しては、自分が事業者に選んでもらえるかという視点のみならず、自分自身が就職先を選ぶという視点を持っているのである。
つまり有能な人材ほど、複数の介護事業者の募集に応募して、応募の受付の対応・採用試験の連絡に際の対応・面接等の試験での担当者の対応などを確認し、採用試験時にその職場の雰囲気や職員の対応の仕方などを観察したうえで、就職先を選ぼうとする傾向が強くなっているのである。
そういう意味では試験を受けているのは、募集に応募してきた人のみならず、募集事業者そのものが求職者から試験を受けているという側面があることを忘れてはならないのだ。この傾向は介護福祉士養成校の卒業生にも強まっていることは、「人材から選ばれる事業者という意識」という記事の中でも解説しているので、そちらも参照願いたい。
それは介護職員という職種が売り手市場であって、どこの介護事業者もその人材確保に悩みを持ちながら経営しているという事情が背景にあることによって生じている事態だが、その背景要因はおそらく今後もずっと解消しないだろう。
つまり求職者から選ばれない事業者は、永遠に人材不足を解消できないということになるのだから、内定辞退者が多い介護事業者は、内定者がその介護事業所を選ばない原因と理由がなんであるかという検証作業を急がねばならないのである。
若者が介護福祉士養成校に入学する人の動機のトップは毎年、「人の役に立ちたいから介護の仕事をしたいと考えた」であるように、人材から人財に成長しうるスキルの高い人ほど、理想とは程遠い劣悪な介護の現実を目の当たりにして、そうした職場では働きたくないと思う傾向が強まるのである。
サービスマナー教育はそうした意味でも重要となってきている。採用面接時に訪れた介護施設の職員の、利用者に対する荒々しい言葉遣いに幻滅して、そこで働く気がなくなったという人の声を放置しているような介護事業者は、人材不足が原因となる倒産予備軍である。まずは今いる職員にサービスマナーの必要性を理解してもらい、サービスの品質向上意識を植え付けなければ、必要な介護人材は確保できない。
受付職員の見下したような態度に不快を感じて、そこで働く気がなくなる人は思った以上に多いので、窓口対応する職員にも十分注意を促さねばならない。
内定辞退者が増えている介護事業者には、このように何らかの問題があることが多いのである。
各種調査によれば、介護職員の不足感を持つ介護事業者の割合は、毎年のように過去最高を更新し続けているのだから、人材獲得競争も激化するのは当たり前である。その競争に勝っていかないと、人材確保で負け組とならざるを得ないが、それはすなわち事業経営の危機に直結する問題なのである。
早急に人材確保に支障を来す問題点を組織の中に内包していないかを確認・是正するシステムを機能させる必要がある。そうしないことには今後の介護事業経営は益々困難となることを自覚してほしい。
なお内定辞退者が増えているのに、なんの対策もとろうとしていない事業者に勤めている職員は、次の働き先を今のうちに探しておいた方が良いといえるかもしれない。
登録から仕事の紹介、入職後のアフターフォローまで無料でサポート・厚労省許可の安心転職支援はこちらから。
※リスクのない方法で固定費を削減して介護事業の安定経営につなげたい方は、「介護事業のコスト削減は電気代とガス代の見直しから始まります」を参照ください。まずは無料見積もりでいくらコストダウンできるか確認しましょう。
北海道介護福祉道場あかい花から介護・福祉情報掲示板(表板)に入ってください。
・「介護の誇り」は、こちらから送料無料で購入できます。
・masaの最新刊「看取りを支える介護実践〜命と向き合う現場から」(2019年1/20刊行)はこちらから送料無料で購入できます。
 しました
しました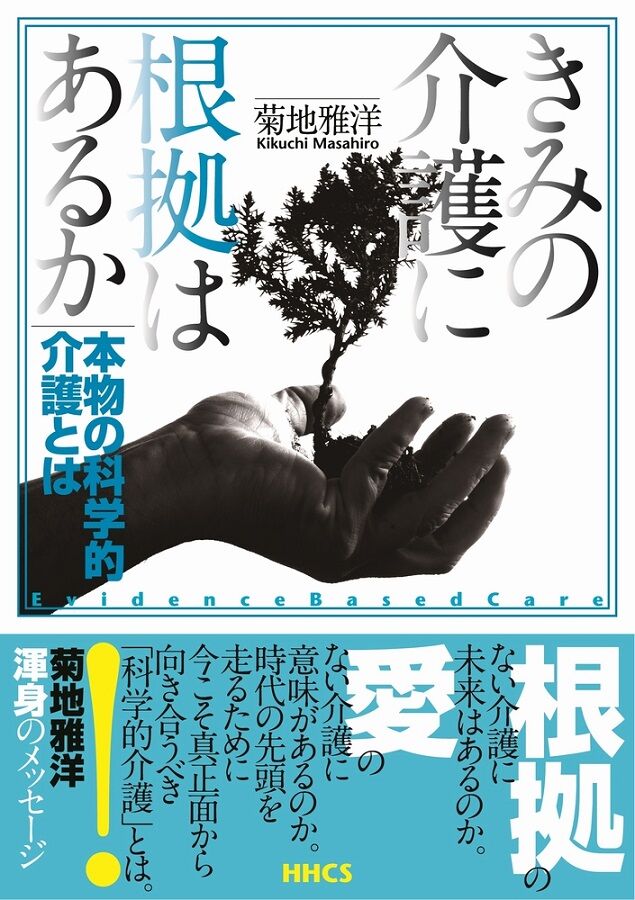
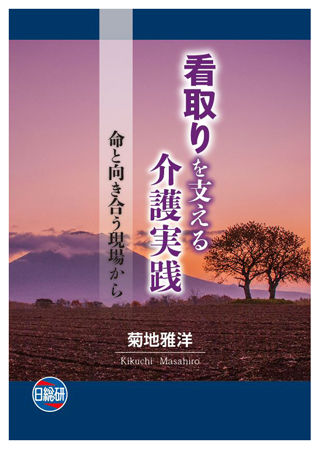

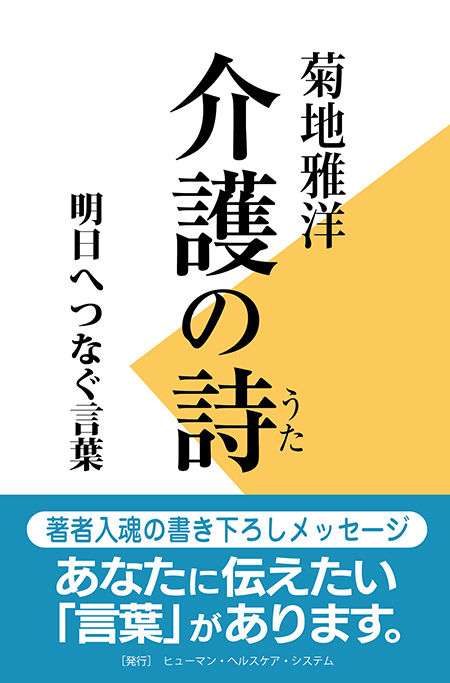
 感動の完結編。
感動の完結編。
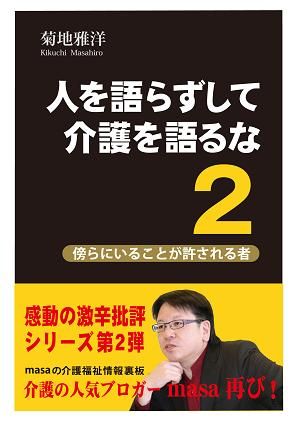
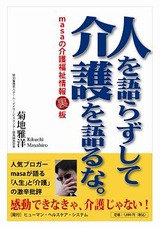
masa
が しました
しました