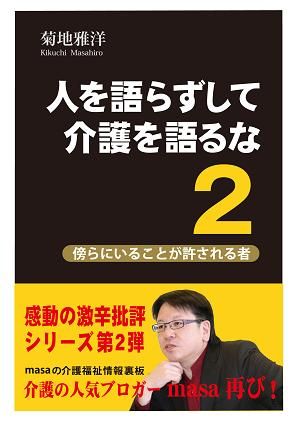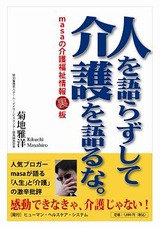【介護の質を上げる工夫の具体例(入浴支援1)より続く】
週2回しか入浴支援を行わない施設では、その2回の入浴日に全員をお風呂に入れなければならず、それが入浴支援を重労働化する最大の原因であることは昨日書いた。
しかしこうした入浴支援の方法には、もう一つ重大な欠陥がある。週2回しか入浴支援しないという環境は劣悪ではあるが、それは最低基準として定められている法令基準であり、それを下回るサービスであっては運営指導対象となる。
しかし週2回の特定日しか入浴支援を行っていない施設であれば、その日に必ず全員を入浴させなければ、この最低基準さえクリアできないことになる。しかし高齢者の方々は、様々な理由で入浴ができない事態が想定される。その時、入浴できなかった人について、特定の入浴日以外にそれらの人の入浴支援を行っているのだろうか?
それを行っていない施設は、この最低基準を護らないという運営基準違反を繰り返していることになる。(※ちなみに僕が独立する前に、医療系サービスの実情を知るために1年だけ体験勤務した千歳市の老健施設では、こうした運営基準違反が常態化していた。)
そのようなコンプライアンスに欠ける運営は、本来許されないわけである。介護施設が最低基準として定められた劣悪な基準さえ守らない場所という批判を世間から浴びないためにも、特定日の入浴機会を逃した際には、翌日に入浴支援ができるなど、入浴支援が毎日でもできる方法の工夫をしなければならない。世間一般並みの入浴機会を確保する以前に、そういう視点も必要になるのだ。
僕が総合施設長を務めていた特養では、毎日入浴支援ができる工夫の一つとしてサービス提供者にとって都合の良い便利な方法である、「分業」をやめるという方法を取っていた。
業務の効率化の名のもとに、介護施設では様々なサービス場面で分業が常態化している。入浴支援の場合は、浴室内の洗身介助・浴槽の出入り介助の担当者と、脱衣所の着脱介助の担当者と、脱衣所まで・脱衣所からの誘導又は搬送介助担当者と、入浴支援を3場面に切り分けて、「分業」する方法が一般化している。
しかしこの方法は、介護業務を支援行為とはかけ離れた、「作業化」する一番の原因であり、流れ作業を促進すだけの結果しか生まないことが多い。そして実のところは「業務の省力化」や「効率化」にはあまりつながらないのが実態である。
なぜなら浴室内介助と脱衣所介助と誘導介助がうまくつながらないからである。結果的に3部門の担当者が、自分の作業の都合だけで自分の担当部門を黙々とこなすだけの結果になり、廊下には脱衣介助を待つ長い行列ができ、脱衣所には浴槽に入る順番を待つ人が裸のまま座って待たされるという状態をつくることになる。待たされる人々にとって、それは至極迷惑な時間であり、人によっては地獄の時間でもあるが、待つことを常態化するというのは、業務ロスが常態化しているという意味でもある。
これを失くすことが、即ち毎日入浴支援ができる方法にもつながっていくのだ。つまり分業をしないということだ。
一人の介護担当者が、居室から脱衣所への誘導及び浴室内介助をすべて担当し、一人の利用者が居室から浴室に移動し、入浴支援を受けて居室に帰るまでの一連の行為をすべて責任を持って行うことで、入浴支援は作業から行為へと転換が図れる。
それでは支援時間がかかり過ぎて、対応すべき人数がこなせないと思うかもしれないが、浴室に今連れていかなくても良い人たちの長い行列を作るという、「業務ロス」がなくなる分、業務は効率化できるのである。
そもそも入浴支援を3場面に切り分けて、「分業」する場合、入浴支援を行うためには同じ時間に入浴支援に携わる人が最低3名必要になる。この3名のタイミングを合わせてやっと入浴支援ができるのである。それは3名同時に、入浴支援以外の業務には携われなくなることを意味している。しかもそこではまだ脱衣所に連れてくる必要のない人を、1時間も前から連れてきて廊下に放置しておくというロスが生まれる。
一人の担当者が一連の入浴支援をすべて行うなら、その担当者が入浴支援をできるタイミングで、いつでも誰かを入浴支援できるわけである。そしてそこには必要のない時間に利用者の移動支援を行うというロスは生じないし、廊下に利用者を放置しておくという不適切な状況も生まれない。
つまり入浴支援担当者は、一斉に入浴支援する必要はなく、例えばA職員が自分の今日の担当者を入浴支援している間に、ほかの職員は入浴以外の業務を行っているということであれば、入浴だけで現場の仕事が手いっぱいになって、ほかの仕事に手が回らないという状態にはならない。勿論、その日の一日の流れを読みながら、ある時間帯は、A職員とB職員の2名が入浴支援にあたって、たまたま浴室でそれぞれの担当者が二人同時に湯船にゆっくり浸かるという場面が生じたって良いわけである。
毎日の入浴支援によって1日に入浴する人の数が減ることに加え、日々の一斉介助をやめ、その日の業務の担当者が、利用者の暮らしに合わせて様々な支援を行うことによって、一つの支援行為だけに手を取られて、ほかの業務に手をかけられないという状態は軽減される。
そこにシフトの工夫を加えて、早出を1名少なくして日勤者もしくは遅出を1名厚く配置する日を造ったり、早出や遅出の勤務時間をユニットごとに変えたりすることで、様々な工夫ができるのである。その結果、配置職員を増やさなくとも、入浴支援ができる日を増やすことは簡単にできるわけだ。
ここに示した方法は、僕が特養で毎日入浴支援をするために取った方法の一つに過ぎず、そのほかにも様々な業務システムの改善で、ケアの品質は向上させることができるのだ。
要はやる気とやるための知恵が大事になるということである。やる気も知恵もない人は、ほかの仕事を探せばよいだけの話だ。
人が足りないからできないのではなく、知恵が足りないからできないのではないかと疑問を持ってほしい。介護の本質の向上のためには、そんな風に自らの姿勢を振り返ることが求められるのである。
それをしない人に、「職業に対する誇り」など得られるわけがなく、そうしようとしない人はプロと呼べるわけもなく、そんな人に全産業平均の給与水準など与える必要もないわけである。
※もう一つのブログ「masaの血と骨と肉」、毎朝就業前に更新しています。お暇なときに覗きに来て下さい。※グルメブログランキングの文字を「プチ」っと押していただければありがたいです。
北海道介護福祉道場あかい花から介護・福祉情報掲示板(表板)に入ってください。
・「介護の誇り」は、こちらから送料無料で購入できます。
・masaの最新刊「看取りを支える介護実践〜命と向き合う現場から」(2019年1/20刊行)はこちらから送料無料で購入できます。
※TSUTAYAのサイトからは、お店受け取りで送料無料で購入できます。
※キャラアニのサイトからも送料無料になります。
※医学書専門メテオMBCからも送料無料で取り寄せ可能です。
※アマゾンでも送料無料で取り寄せができるようになりました。
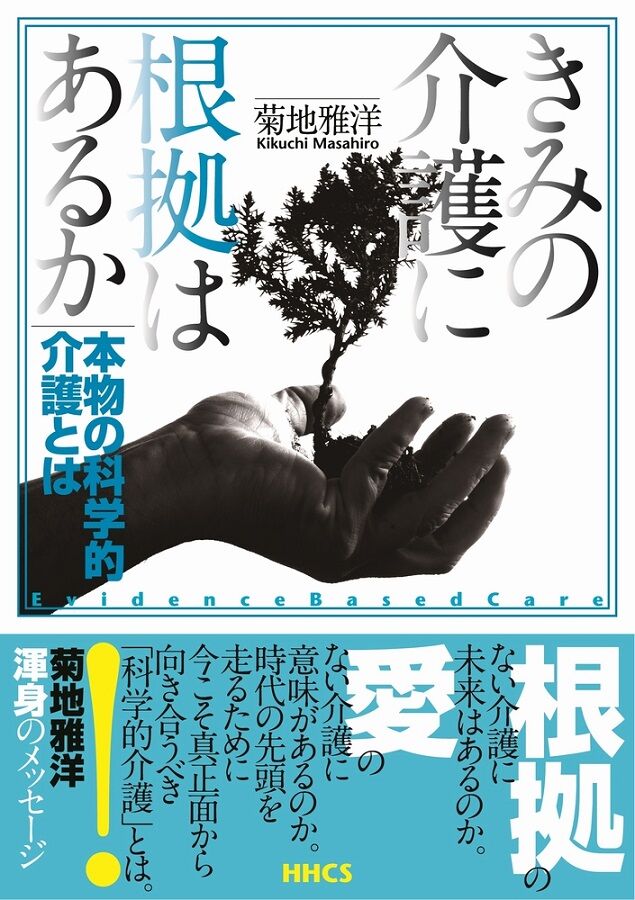
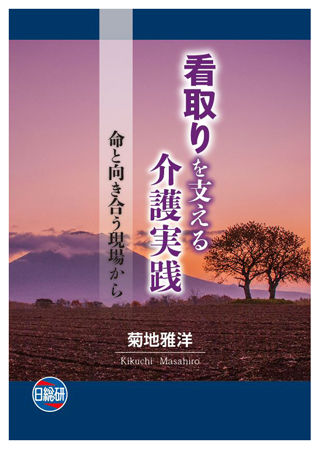

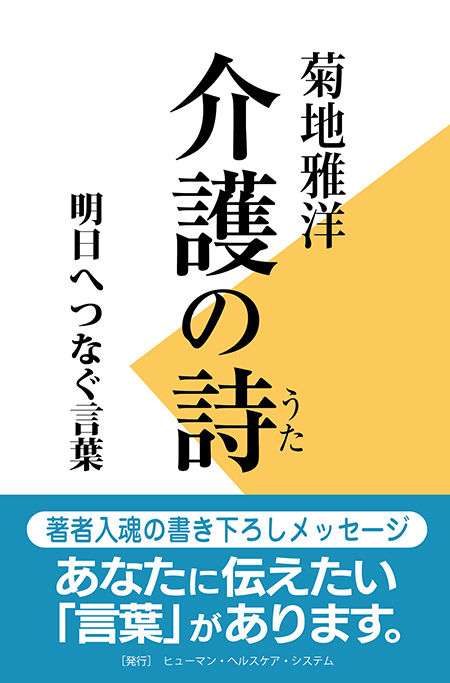
 感動の完結編。
感動の完結編。