アミーユ川崎幸町で隠し撮りされたビデオには、殺人事件の犯人以外の複数の職員が、利用者を罵倒しながら乱暴に取り扱う姿が映されていた。
その姿は虐待そのものであるが、こうした暴言は、日常会話の乱れから始まり、乱れた言葉がエスカレートして心を乱し、その心の乱れから感覚麻痺が生じた結果ではないだろうか。
しかしあの隠し撮り映像を見て、「あれほどひどい状態は自分たちの職場とは無縁だ。」と安心してよいのだろうか。「それでは、どの程度までならば許されるのか?」と考えたとき、自分自身の対応が、顧客サービスとして適切かどうかという線引きしかできない。介護サービスにおいて職員が利用者に接する際にも、利用者の尊厳を損なわないという意識が必要で、そのための最低限のマナーが求められ、それは顧客対応としてふさわしい態度を守ることでしか実現しない。
そのために僕は、「介護サービスの割れ窓理論」を提唱し続けているわけであるが、僕とほとんど同じ考え方で、介護サービスの場でも、福祉援助職としてサービスマナーを実践するという考え方を示し、教本を作って、「サービスマナー研修」を行っている機関がある。
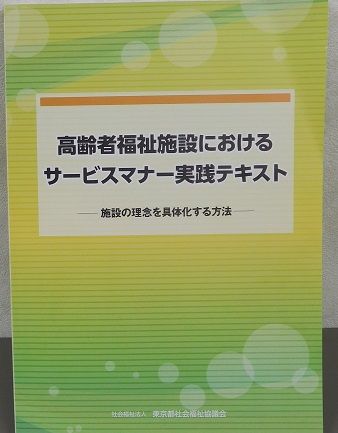 それは東京都社会福祉協議会であり、同協会が発行しているテキスト教本が、「高齢者福祉施設におけるサービスマナー実践テキスト〜施設の理念を具体化する方法」(編著者:岩本 操・武蔵野大学人間科学部准教授)である。
それは東京都社会福祉協議会であり、同協会が発行しているテキスト教本が、「高齢者福祉施設におけるサービスマナー実践テキスト〜施設の理念を具体化する方法」(編著者:岩本 操・武蔵野大学人間科学部准教授)である。ここでは、「サービスマナーは、施設の理念を具体化する行為」、「サービスマナーの実践は、あらゆる業務の基盤となる専門的行為」と述べ、「親しみやすさと馴れ合い」を混同することの危険性を指摘している。
そして、「丁寧な言葉遣いや敬語を使っても、親しみやすさは十分伝わる」と指摘し、介護施設で若い職員が、利用者に対して、「〜だよ」、「何をやっているの」などと話しかけている状態は、言葉の乱れであり、馴れ合いだとして、「マナーは自分の損得ではなく、相手の得にあるわけですから、これではサービスマナーの実践とは言えません。」としている。
これを読んで気が付いた人がいるだろう。それはこの内容が、僕が提唱する「介護サービスの割れ窓理論」とほぼ同じであり、僕が講演などで主張・提言している内容と、まったく同じことだということである。
このテキストが、僕の意見を参考にして作られているわけではない。また、僕自身は20年以上前から「介護サービスの割れ窓理論」を提唱していることでもわかる通り、このテキストを参考にしているわけでもない。
そうであるにもかかわらず、両者の主張が非常に似通って、部分部分を取り上げると、全く同じ主張・提言となっているということを考えると、言葉を正しくして、お客様に対してふさわし対応に心がけるということは、決して突飛で特別な考え方ではなく、ごく当たり前の考え方であり、医療・保険・福祉・介護の場で、そのことが守られていないことの方がおかしいということだ。
顧客に対して丁寧な言葉や態度で接することができない状態が、いかに異常であるかという証明でもある。そのことが守られていない職業とは、未成熟で幼稚な職業であるともいえよう。
サービスマナーの確立は、介護サービスの品質の向上とイコールである。今後、介護サービスの利用者に増えることが予測される「団塊の世代」の方々は、そうしたマナーには我々の世代よりも敏感である。
そうであれば介護サービスの場で、言葉遣いに気を遣わず、乱れた言葉で話しかける職員に対し不快感を持つ人は多くなるし、サービスマナーに気を遣わない職員から、介護支援を受けることを悲しむ人も多くなるだろう。
その結果が選ばれない事業ととなって、事業経営ができなくなることで終わるならば、それは自己責任だから良いだろう。
しかし介護サービスを必要とする人の数が増える時期なのだから、そうした品質の悪いサービスを使わざるを得ない人達がいることを考えると、マナーのないサービスを使うことに、陰で泣きながら、「こんな思いをするなら、もっと早く死ねばよかった」という嘆きの気持ちを抱きつつ、心遣いのない、マナーの低いサービス提供を我慢せねばならない人が出てくる。
介護という職業が、そのような状態を創りだしてよいのだろうか。よいはずがない。だから僕らの時代で、介護のスタンダードを変え、ごく普通に丁寧な言葉遣いがされ、サービスマナーをもって対人援助に携わるというスタンダードを創り、いつの日か「言葉づかいとか、マナーが議論されるような時代があったんだ」と言える状態にしなければならない。
顧客である利用者に対し、丁寧な言葉で対応するというのはごく当たり前のことで、そんなことがよいのか悪いのかということの説明が必要とされたり、議論になったりする職業がどうかしているのだ。
なおこのテキストは、東社協から1.429円+税で購入できる。1冊あればそれを参考に施設内研修も可能となろうから、是非職場内研修などで、サービスマナーを学んでいただきたい。その時には、ぜひ介護サービスの割れ窓理論もご紹介いただきたいと思う。
このテキストの編著者:岩本 操・武蔵野大学人間科学部准教授(下の画像左から2番目)とは、いつかサービスマナー講座で、コラボしたいとお話ししてきた。ぜひ実現したいものである。

3/11(金)東社協主催研修の講演後のオフ会。東社協の櫻川施設長(左)と堀施設長(右)に挟まれた、僕と岩本先生。)
※もう一つのブログ「masaの血と骨と肉」、毎朝就業前に更新しています。お暇なときに覗きに来て下さい。※グルメブログランキングの文字を「プチ」っと押していただければありがたいです。
介護・福祉情報掲示板(表板)
「介護の詩・明日へつなぐ言葉」送料無料のインターネットでのお申し込みはこちらからお願いします。
「人を語らずして介護を語るな 全3シリーズ」の楽天ブックスからの購入はこちらから。(送料無料です。)
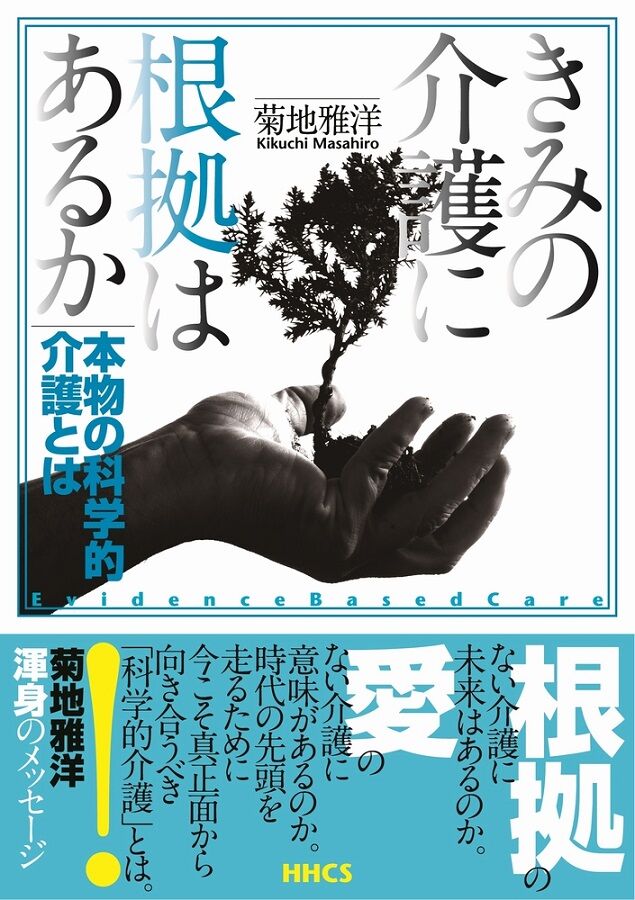
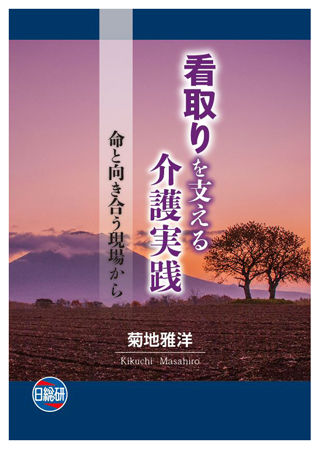

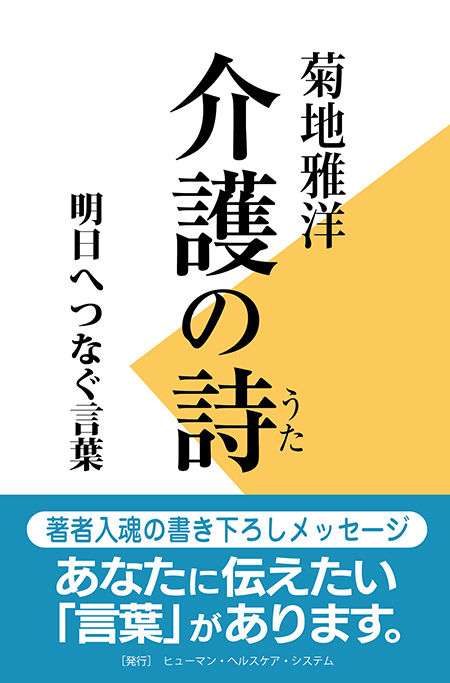
 感動の完結編。
感動の完結編。
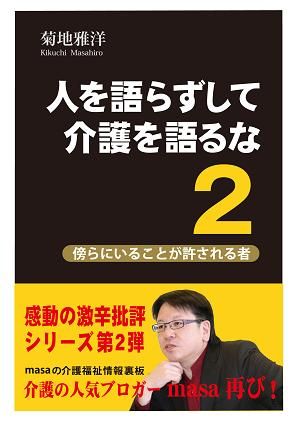
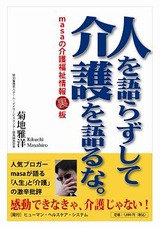
介護サービスに従事して気が付いたのは非正規雇用の増加と社会性の低さに問題が有るのでは?と常々思っています。バランスの取れた食事をする高齢者を目の前にして少ない時間でカップ麺食べ、塩おにぎりだけの職員もいます。訳あり職員が多く夜勤の際には幼い子供を留守番させ「最近子供が起きれなくて学校に行かなくなった」等も聞きます。生活の安定が保証されない現状は精神的にも辛いです。
汚い言葉を使う職員は社会経験が乏しく高校中退や離婚するまで企業経験無い主婦が目立っていました。
福祉大卒も一部に「大卒の肩書きが欲しかっただけ」の方もいました。仕事しません。アミーユが実は特別と思えません。私は50代女性に殴られました。理由は他の職員とその女性が殴りあいの喧嘩になりかけ「止めて下さい」と止めたら殴られました。理性なんて無い世界なんだなと驚きました。
新規参入の民間ホームは経営者が介護については営利中心なので教育なんて有りませんでした。ヘルパー二級が聴診器で診察していても注意もなく無法地帯でした。人件費削減の為に職員は夜勤夜勤明夜勤明休(16時間夜勤一人勤務)等、どこの北朝鮮なんだろうと思わされました。勿論、職員は定着しません。言葉だけでなく人間関係も乱れてました。根底から改善しないといつまでも駄目な業界だと思います