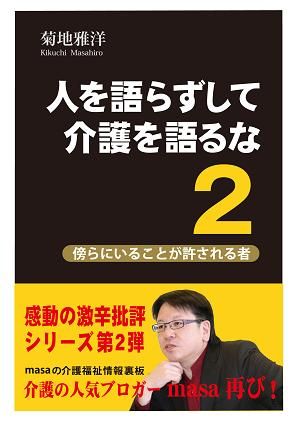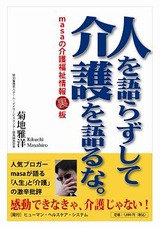拙著、「人を語らずして介護を語るな2〜傍らにいることが許される者」(通称:黒本)の140頁に、「異説ケアマネ論〜何でもする人になるな」というコラムを書いている。
その中で僕は、介護支援専門員はオーケストラいえば、タクトを振る指揮者役であり、介護サービスをコーディネートするに際し、各サービス事業所の担当者や、施設における介護支援者と同じような直接援助技術を持つ必要はないし、計画された行為自体を自信が行う必要もない、としている。
さらに、通所サービス利用中に救急搬送が必要となり、誰も付き添う人がいない場合はどうしたらよいかという例を取り上げて、その場合は第1義的には、そのサービスを提供していた事業者が「人としての責任」・「直接サービス提供している事業者の責任」において対応するべきであり、その後の対応をどうするかという部分は、総合的に生活支援している介護支援専門員が中心になって具体的方策を考えるとしても、その場における通院対応は通所サービスの責任であると書いた。支援チームの要役を担うケアマネだとしても、こうした場合の家族が対応不可能な通院まですべてケアマネの責任や役割として、「しなければならない」ということではないはずだ。
家族ができないことを、なんでもケアマネジャーに任せればよい、という考え方は「違う」という共通理解を形成すべきであるとも書かせてもらった。
介護支援専門員は、なんでも任せてよい便利屋ではないのである。
しかし、同時に介護支援専門員は、相談援助の専門職として、利用者の生活全般の課題を解決するための総合的支援が求められている。この部分は、まさにソーシャルワーカーとしの役割なのだから、「自分の仕事の守備範囲ではない」と放り出すことは許されないのである。
何でも屋ではないが、相談援助の専門職としての総合的支援の一環として関わらねばならない部分があることも事実であり、この違いの判断ができるかどうかというのも、ケアマネのスキルということになってくる。
過日、フェイスブックでつながっている方から聴いた話である。その方のお母さまが、認知症となって介護支援を受けているのであるが、以前は訪問診療をしていた、「かかりつけ医師」がおり、介護更新認定などの「主治医意見書」は、その医師が書いていたのであるが、様々な事情があって、現在は訪問診療も中止しており、かかりつけ医師がいない状態で、介護更新認定の時期を迎えたとき、だれに主治医意見書を書いてもらうかを相談したところ下記のような状態になったというのである。
ケアマネさんに尋ねると「市に尋ねたら」と言われ、市役所に行って尋ねると、「地域包括支援センターへ」と言われ、地域包括支援センターへ行くと「お母さんを見ているケアマネさんに聞いてください」と言われ、一周回って、何の回答も得られないことが何度かあり、聞くのはムダ、と諦めていました。
こんな笑い話のような「現実」があってはならない。
介護保険法第二十七条3では、主治医の意見書について次のように定めている。
市町村は、第一項の申請があったときは、当該申請に係る被保険者の主治の医師に対し、当該被保険者の身体上又は精神上の障害の原因である疾病又は負傷の状況等につき意見を求めるものとする。ただし、当該被保険者に係る主治の医師がないときその他当該意見を求めることが困難なときは、市町村は、当該被保険者に対して、その指定する医師又は当該職員で医師であるものの診断を受けるべきことを命ずることができる。
このように主治医師の意見を求める、「責務」が市町村にあるのだから、市町村の窓口で相談するのは当然である。しかし指定医を持たない市町村もあるのだし、自分が担当している利用者が住む地域が、指定医がいる市町村であるかどうなのかという情報は、相談援助の専門職として、当然確認しておかねばならない情報である。そして指定医がいない地域であれば、自分が担当する利用者に、「かかりつけ医師」がいない場合の想定を行い、その場合にどうするのかという想定も行っていて当然である。
何よりも介護認定という、保険給付に必要不可欠な申請行為のサポートを、自分の役割ではないと考えるような介護支援専門員であっては困るわけである。そうであれば、指定医師をどうするのかという相談を受けて、まず市町村窓口で、紹介してくれる医師がいるかどうかを確認してみましょうというアドバイスを行うことがあってもよいと思うが、そのときに、利用者の家族の申請責任であると丸投げするのではなく、その確認や申請のサポートを行うという方向から、「たらいまわし」にならないように、市町村あるいは地域包括支援センター(委託事業者であっても市町村の機関であることは変わりないのだが。)との折衝行為に、ケアマネとして同行して調整するという行為が必要な場合もあり、これは一連のケアマネジメントの中に含まれる行為であろう。
もともと介護保険制度における居宅サービスのケアマネジメントは、様々な社会資源と利用者をつなぐ際の、申請行為を含めたマネジメントを、居宅介護支援事業所の担当介護支援専門員という専門職に担わせ、実質的に窓口を一つにして、利用者の利便性を図るというワンストップサービスの考え方があった。
その考え方は極めて正しい考え方で、現にそのことによって、利用者は地域の中で暮らす際に、自分を護ってくれる専門家、自分を護ってくれる担当者を得ることになったのである。
しかしこのシステムが予防給付と介護給付の分離により崩壊してしまったが、だからと言って介護支援専門員自身が、この窓口をさらに増やすかのような行為に走り、利用者の利便性を損なってはならないのである。
利用者の暮らしを護る専門職として、社会資源と利用者をつなぐ調整役としての責任を考えるのなら、当然介護更新認定時の申請手続きがスムースに行われ、利用者や家族に戸惑いや不安感を与えないようにサポートするのが介護支援専門員の役割である。
そうした責任感を持たない介護支援専門員は必要とされないであろう。
和歌山地域ソーシャルネットワーク雅(みやび)の皆さんが、素敵な動画を作ってくれました。ぜひご覧ください。
介護・福祉情報掲示板(表板)
4/24発刊「介護の詩・明日へつなぐ言葉」送料無料のインターネットでのお申し込みはこちらからお願いします。
「人を語らずして介護を語るな 全3シリーズ」の楽天ブックスからの購入はこちらから。(送料無料です。)
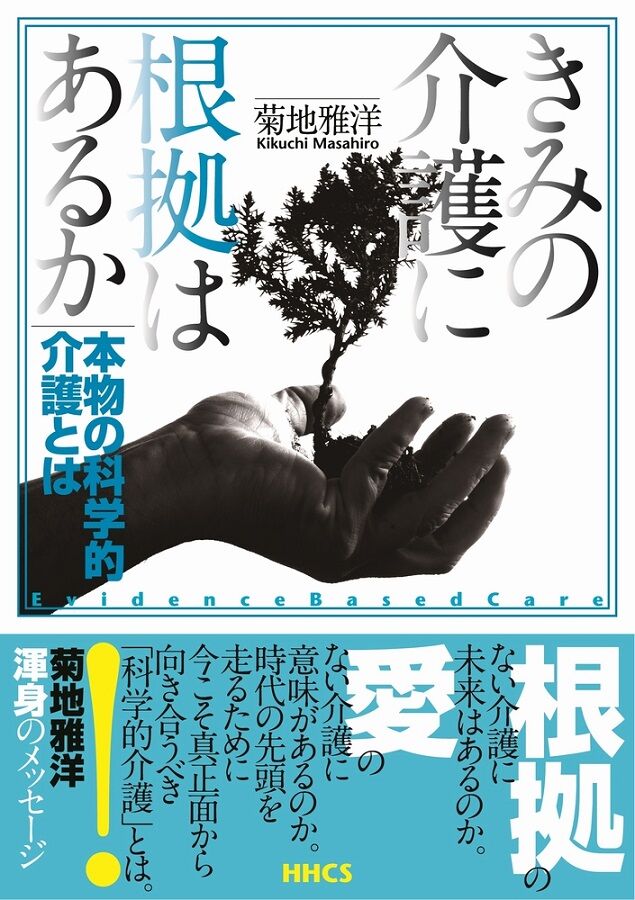
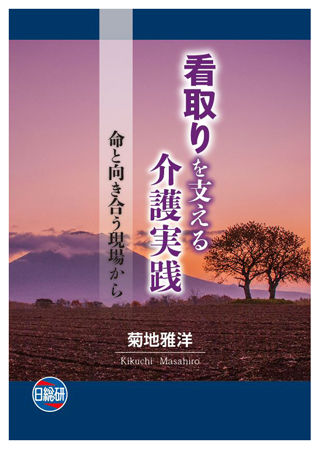

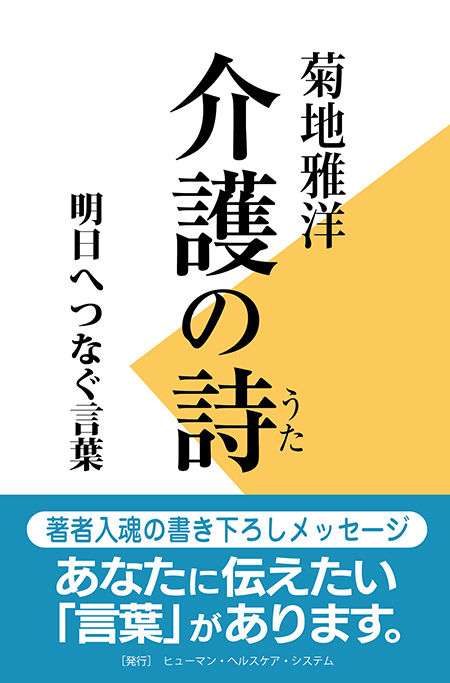
 感動の完結編。
感動の完結編。