昨日の北海道新聞・朝刊の生活面(15面)に「特養の入所順 決め方は?」と題して、当施設の入所判定委員会を取材した内容が中心となっている特集記事が掲載された。

この取材を受けた理由は、取材目的が、特養の待機者が増え続けている中で、その入所順番がどのように決められているのかを実際に判定委員会の議事進行場面を取材して実態を報道したいというものであり、それに応えて正しい情報を道民の皆さんに知っていただきたいと思ったからである。
その背景にはたくさんの特養待機者が居られる中で、待機者やその家族がなかなか特養入所に繋がらず、待機期間が長期化する実態があり、それらの人々が本当に公平な判断基準で入所順位が決定されているのか、有力者の圧力等で入所順位が変わるのではないか、施設の収入などに関連して都合よく順位決定しているのではないのか等の不安や不満を持つ場合があるからだと思う。そのために真実はどうなっているのかを取材したいという意味がある。
特養の入所順の決定については、法令上次のような定めがある。
指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準について(平成12年3月17日 老企第43号)
5.入退所(2)同条第2項は、入所を待っている申込者がいる場合には、入所して指定介護福祉施設サービスを受ける必要性が高いと認められるものを優先的に入所させるよう努めなければならないことを規定したものである。また、その際の勘案事項として、指定介護老人福祉施設が常時の介護を要する者のうち居宅においてこれを受けることが困難な者を対象としていることにかんがみ、介護の必要の程度及び家族の状況等を挙げているものである。なお、こうした優先的な入所の取扱いについては、透明性及び公平性が求められることに留意すべきものである。
この規程に基づいて、ほとんどの施設では(全部と書かないのは、例外があるかもしれないという意味で、僕自身が例外を知っているという意味ではない)、入所順位の決定基準を定め、入所判定委員会において審査し入所決定しているはずである。この過程で老企43号通知に定められた「透明性及び公平性」が担保される状況が証明できなければ、運営基準違反として指導対象になるものである。
当施設は北海道老施協が作成した入所判定基準に、施設独自の2次判定基準を付け加え、それを元に市の担当課職員など外部の委員が参加して、公明正大に入所順位を決定しているので、何も隠すことがないため、積極的にこの取材に応じた。その取材をもとにした記事となっている。
当施設の入所ルールは、リンク先を貼り付けているのでそちらで確認して欲しいが、その中の入所順位決定に影響する勘案事項として、「6.お客様の要医療状態と、施設がもつ医療機能とのマッチングへの配慮。」という項目がある。これについて記事では、「待機者の身体状況によっては入所できないこともある。」と解説した上で、道内の別の施設が、胃瘻からの栄養補給が必要な人や、インスリン注射を必要としている人の数をあらかじめ決めて、「医療ケアの必要性の高い人」については、その上限を超えないように入所調整している状況を紹介している。
しかしこの記事を読んだ、道内の歯科医師がネット上で、「誤嚥性肺炎をくり返し入院している場合も、医療依存が高いから入所できないことになるのか」、「入院が繰り返されると施設収入が減額となるから医療依存が高いとして入所できないのか」などと発言している。まったく記事のななみ読みにも程がある。
入所判定は、その時点の現況に基づいて判断する以外にないので、誤嚥性肺炎を繰り返していても、判定の時点で安定しておれば、その状態で判定するしかないし、そもそも委員の半数が市の担当課職員など外部委員で占められている委員会で、施設収入の多寡を理由にした入所判定があり得るのかという常識を考えれば、そんなことはできないと考えるのが当然である。
歯科医師が指摘した理由は、正当な理由による入所拒否に該当しなことも明らかである。医療とのマッチングを考えるのは、「排除の論理」ではなく、特養という看護職員がいない時間帯がある施設における、法に基づいた適正サービスを担保するためのものでしかない。
経管栄養の一部行為が一定条件下で介護福祉士等に認められる法改正が行われたといっても、インスリンなどは医療行為として、看護師等の有資格者にしかできない行為であることに変わりはないのだし、看護師のいない時間帯にインスリン注射が必要な人を受け入れることができないのは、「正当な理由」である。そもそも施設の医療行為対応力の上限までしか、医療ニーズの高い人を受け入れられないというのは、利用者に対する適正サービスという側面から考えられている問題であり、対応力を超えた受け入れは、医療事故等のリスクに利用者を晒すことと考え、そんなことがないように考慮されているものである。
そうした事情を知ることもなく、ホームページ等で公開されている各施設の入所判定ルールを読んで裏をとることもなく、報道記事を斜め読みして、悪意に満ちたような情報を垂れ流すことは、世間の偏見を助長することにほかならない。SNSなどを通じて、自由な意見を述べるのは良いが、もっと建設的な議論になるように、根拠に基づいた発言をしていただきたいものである。
ただ、この特集記事の中では、施設名は出されていないが、札幌市内の施設で、胃瘻増設者を一切受け入れていないという例が示され、その理由が、「最期まで口から食べてもらい、自然なみとりを行うことを方針にしている丈です。胃瘻の方から申し込みがあれば、療養型の施設などを紹介しています。」と書かれている部分がある。
僕の施設や、医療ニーズの高い人の数の上限を定めている施設は、その名称が記事に書かれているが、この施設だけは匿名で施設名が書かれていない。記事を書いた記者も、この主張と、その他の施設の主張に何かしら隔たりを感じたからではないだろうか?
僕もこの施設の考え方には違和感を覚えざるを得ない。そのことはまた別な問題なので、月曜にも論評させてもらいたい。
介護・福祉情報掲示板(表板)
「人を語らずして介護を語るな THE FINAL 誰かの赤い花になるために」の楽天ブックスからの購入はこちらから。(送料無料です。)
「人を語らずして介護を語るな2〜傍らにいることが許される者」のネットからの購入は
楽天ブックスはこちら
↑それぞれクリックして購入サイトに飛んでください。
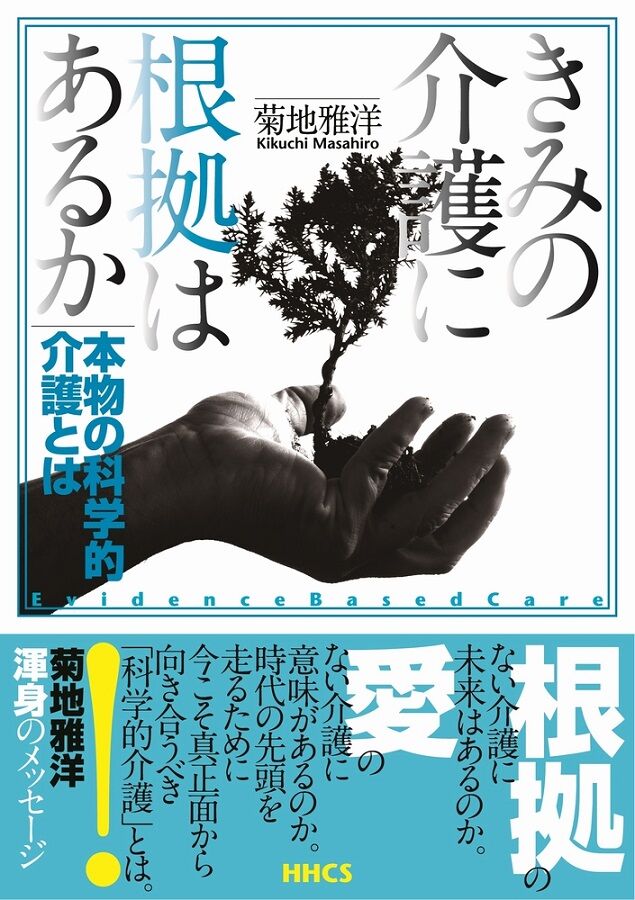
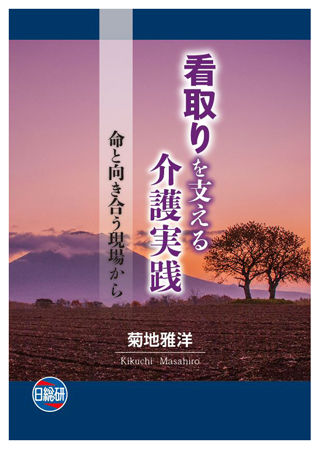

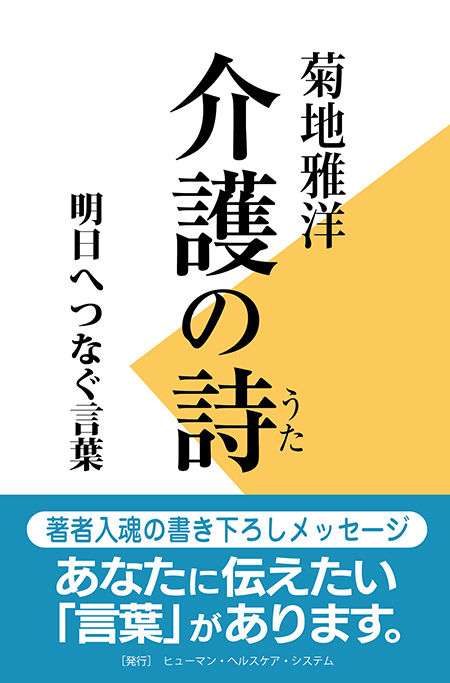
 感動の完結編。
感動の完結編。
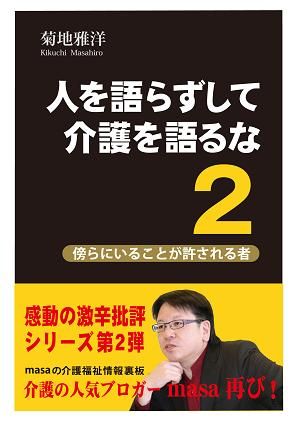
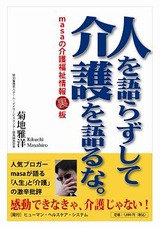
masaさんのブログから、ちよっとズレますが、
医療と介護の狭間の家族で悪戦苦闘しています。麻薬の内服コントロール困難でSPO2低下にて救急搬送。
「特養は、家です。病院ではありませんから医療的治療体調者は対応困難です。」
「病院は、治療の場。認知症の手のかかる人は、癌の末期でも対応困難です。」
そのような行き場のない認知症高齢者を抱える家族は、我が家だけではないと思わます。
そのような時に「Drから退院説明」とのことで、入院先へ向うと、「危篤です。」・・・
私にとっては、先週、本人の大好きな「魚釣りができ、介護保険外で泊りができるデイサービス。」より、
救急搬送した時から予想していましたが、認知症の為、「困難事例」で入院先も悪戦苦闘されていたと思われます。
それが、「日本の医療と介護の狭間」の現状です。
私は、お互いの立場が理解できるので、間に立たされストレス!
しかし、一般人の家族は、「認知症だから?治療に抵抗するから?帰宅願望があるから?・・わからん?」
そんな中、看護師さんは、多忙のなか、一生懸命です。
不思議にも意識が回復し、吸引後に男性看護師さんに苦しかったせいもあり、「なんだ、馬鹿野郎!」の発言が出て、
「言葉が出て、よかったね!」と返答して下さり、ありがたい気持ちでいっぱいでした。
お互い、それぞの立場で頑張りましよう!