社会福祉援助者として、利用者との面接場面で持つべき「必要なスキル」に関するいくつかの記事を過去に書いてきた。
(参照:「面接の技法」「共感的理解とは何か」etc.)
そこでは「話し上手になるよりも、聞き上手になることが大事」であることや、「良き指導者ではなく、良き聞き手になれ」という主張を繰り返してきた。
このことは、相談員やケアマネジャーだけではなく、看護職員や介護職員も同様に持つべき視点だと思う。現場の生活場面での「日常会話」もある種の面接場面と言えるから、利用者がくつろいで、相談員やケアマネや看護師やケアワーカーに「自分が最も心にひっかかっているもの」「他人に話したことがない気持ち」を話すことができることは、両者の信頼関係を築く上で重要だからである。
そうした利用者の心の叫びを深く傾聴することにより、利用者は今まで抑圧してきた思いを「発言」することができ、そのことにより浄化することができる。このことを専門用語では「カタルシス」と呼び、その結果として利用者自身は精神的安定を獲得することも可能となる。
そうした場面で話を傾聴する者にとっては、援助者自身がどのような職種であろうと、利用者が信頼して心の中身を吐露してくれることによって、自分の予測を超えた利用者の状況を推察し得るという意味をもつこととなり、貴重な情報を得る結果となり得る。
だから、こうした場面では利用者自身が自由に気兼ねなく話しをすることができることが重要である。
しかしここで間違ってはいけないことは、「利用者が自由に話せる」ということは、社会福祉援助者が沈黙して、何の介入もせずコントロールしないことではない。
利用者は、自身の心に最もひっかかっていることや、あるいは秘密にしておきたいことを自由に話すことができることによって、自分自身の問題が何なのか理解できるようになるかもしれないし、その原因も明らかになるかもしれない。社会福祉援助者が大事にする傾聴とは、その目的を達するためのものであり、そのために利用者が自由に話すという意味があるのだから、社会福祉援助者はニーズに接近するように方向付けを行う必要も一方ではあるという理解が必要だ。
だから自由に話すとは、一方的に援助者が聞くだけで、言葉を発しないことを意味しないし、傾聴とは聞く側が黙ることを意味しない。
その時に必要なことは、利用者の発する思いに歩調を合わせた「返事」を随所に返したり、必要不可欠な「質問」を随所に入れることである。利用者の生活課題やニーズや、それに向かう目標がどの方向にあるのかという道標となり得る方向に向けた質問はあってよいのである。
では具体的に相手の思いに歩調を合わせて、向かうべき方向を示す質問とはなにか?
これは「個別の状況に応ずる」と言われてしまえばそれまでで、それ以上何もなくなり、それは職人技あるいは神の領域になりかねない。
高齢者等の生活支援の場合に、そのような職人技や神技を持たなくとも、一定の援助技術と知識を持つものであれば誰でもそういう道標となる方向付けができるように標準化されたツールの一つが「アセスメントツール」である。生活課題を引き出し、ニーズを見つけるために必要な情報を得るためのツールとして、それは存在しており、最低限知るべき情報がそこには標準化されている。
逆に言えば、あのアセスメントシートをすべて埋めるだけの質問攻めをするのがアセスメントとかケアマネジメントではない。
日常会話や面接場面の中で、利用者がストレスを感じず、自由に話していると感じながら、その中で一定の方向性を示す質問を織り交ぜながら、利用者が自身の課題やその問題に気づくためのコミュニケーションが求められているのである。
相手の話を遮ってまで質問する必要はないし、それは傾聴とは程遠いものであるが、一方、何の工夫もせずに相手がたどり着こうとする答えのある場所から遠い場所をさまようことを放置することは社会福祉援助の専門家の対応としては「貧しき対応」と言わざるを得ないのである。
どちらにしても社会福祉援助者であれば、魂を込めて相手の話に耳を傾けるという姿勢を常に持たないとどうしようもないということだ。
↓下のボタンをプチっと押して、応援お願いします。
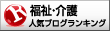

↑こちらのボタンをクリックしていただくと、このブログの解析がみられます。
介護・福祉情報掲示板(表板)
(参照:「面接の技法」「共感的理解とは何か」etc.)
そこでは「話し上手になるよりも、聞き上手になることが大事」であることや、「良き指導者ではなく、良き聞き手になれ」という主張を繰り返してきた。
このことは、相談員やケアマネジャーだけではなく、看護職員や介護職員も同様に持つべき視点だと思う。現場の生活場面での「日常会話」もある種の面接場面と言えるから、利用者がくつろいで、相談員やケアマネや看護師やケアワーカーに「自分が最も心にひっかかっているもの」「他人に話したことがない気持ち」を話すことができることは、両者の信頼関係を築く上で重要だからである。
そうした利用者の心の叫びを深く傾聴することにより、利用者は今まで抑圧してきた思いを「発言」することができ、そのことにより浄化することができる。このことを専門用語では「カタルシス」と呼び、その結果として利用者自身は精神的安定を獲得することも可能となる。
そうした場面で話を傾聴する者にとっては、援助者自身がどのような職種であろうと、利用者が信頼して心の中身を吐露してくれることによって、自分の予測を超えた利用者の状況を推察し得るという意味をもつこととなり、貴重な情報を得る結果となり得る。
だから、こうした場面では利用者自身が自由に気兼ねなく話しをすることができることが重要である。
しかしここで間違ってはいけないことは、「利用者が自由に話せる」ということは、社会福祉援助者が沈黙して、何の介入もせずコントロールしないことではない。
利用者は、自身の心に最もひっかかっていることや、あるいは秘密にしておきたいことを自由に話すことができることによって、自分自身の問題が何なのか理解できるようになるかもしれないし、その原因も明らかになるかもしれない。社会福祉援助者が大事にする傾聴とは、その目的を達するためのものであり、そのために利用者が自由に話すという意味があるのだから、社会福祉援助者はニーズに接近するように方向付けを行う必要も一方ではあるという理解が必要だ。
だから自由に話すとは、一方的に援助者が聞くだけで、言葉を発しないことを意味しないし、傾聴とは聞く側が黙ることを意味しない。
その時に必要なことは、利用者の発する思いに歩調を合わせた「返事」を随所に返したり、必要不可欠な「質問」を随所に入れることである。利用者の生活課題やニーズや、それに向かう目標がどの方向にあるのかという道標となり得る方向に向けた質問はあってよいのである。
では具体的に相手の思いに歩調を合わせて、向かうべき方向を示す質問とはなにか?
これは「個別の状況に応ずる」と言われてしまえばそれまでで、それ以上何もなくなり、それは職人技あるいは神の領域になりかねない。
高齢者等の生活支援の場合に、そのような職人技や神技を持たなくとも、一定の援助技術と知識を持つものであれば誰でもそういう道標となる方向付けができるように標準化されたツールの一つが「アセスメントツール」である。生活課題を引き出し、ニーズを見つけるために必要な情報を得るためのツールとして、それは存在しており、最低限知るべき情報がそこには標準化されている。
逆に言えば、あのアセスメントシートをすべて埋めるだけの質問攻めをするのがアセスメントとかケアマネジメントではない。
日常会話や面接場面の中で、利用者がストレスを感じず、自由に話していると感じながら、その中で一定の方向性を示す質問を織り交ぜながら、利用者が自身の課題やその問題に気づくためのコミュニケーションが求められているのである。
相手の話を遮ってまで質問する必要はないし、それは傾聴とは程遠いものであるが、一方、何の工夫もせずに相手がたどり着こうとする答えのある場所から遠い場所をさまようことを放置することは社会福祉援助の専門家の対応としては「貧しき対応」と言わざるを得ないのである。
どちらにしても社会福祉援助者であれば、魂を込めて相手の話に耳を傾けるという姿勢を常に持たないとどうしようもないということだ。
↓下のボタンをプチっと押して、応援お願いします。
↑こちらのボタンをクリックしていただくと、このブログの解析がみられます。
介護・福祉情報掲示板(表板)
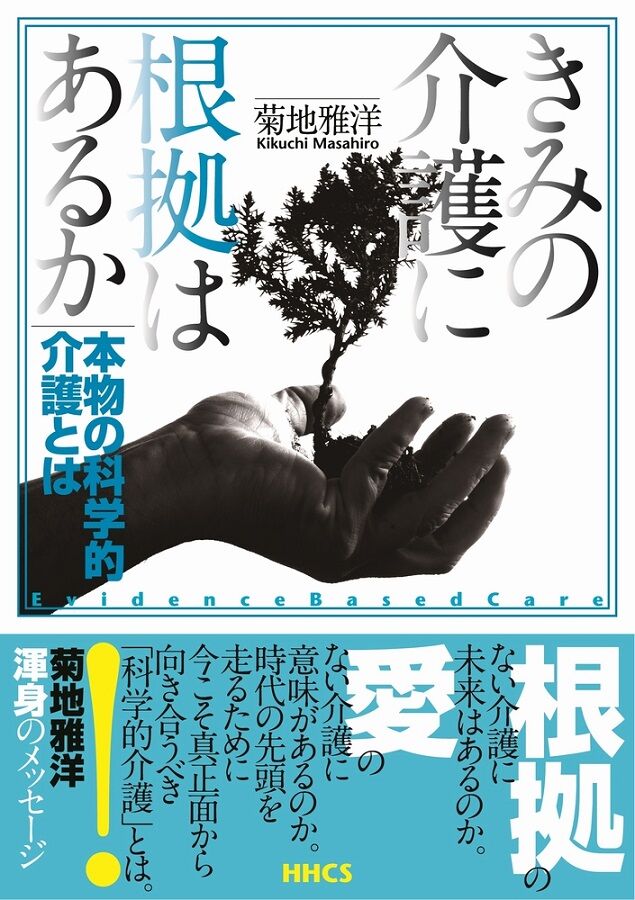
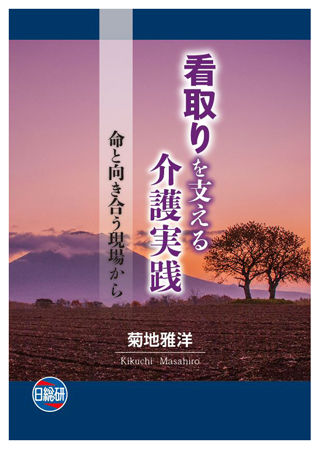

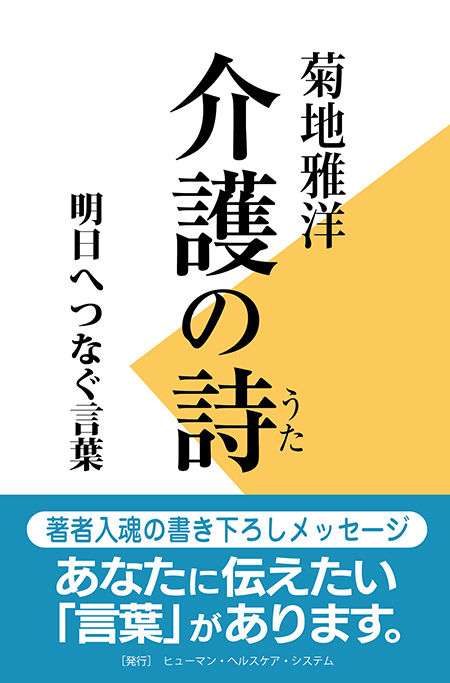
 感動の完結編。
感動の完結編。
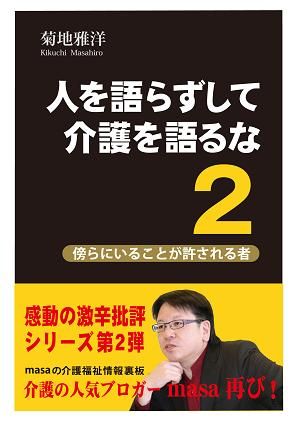
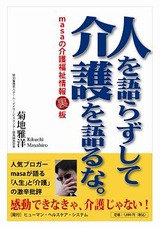
カウンセリングの大家でもあるカール・ロジャースが有名。
カール・ロジャースが面接している場面のVTRが残されていて、それを見たことがありますが、ロジャースはけっして黙っていません。
文字通りactiveにクライエントにかかわり、クライエントの話したいこと(本心)を引き出すためにどんどんと質問を投げかけています。質問を投げかけるのは「自分が知りたいから」ではなく、クライエントに考えてもらう、クライエント自身が一番訴えたいことに木がつけるような「質問」をしているのです。
だからこそ「active listening」となるのです。
それを理解していないと「傾聴」も勘違いしてしまいます。