ソーシャルケースワークの原則と呼ばれる「バイスティックの7原則」については、社会福祉士の国家試験でも何回も手を変え、品を変えして繰り返し出題されている。
それだけこの原則が大事であるということだろうし、その原則を守る姿勢が援助関係を形成するために必要であるということについては、時代が変わった現代社会おいても同様であると考えられているということであろう。
僕もこのブログの中で、その原則に触れた話題を何回も書いており、その原則の意味や理解の仕方についても説明したりしている。(参照:この原則に触れた過去のブログ)
しかしこの原則がケースワークのすべてで、少しでもこの原則に則らない行為や考え方は間違っていて、社会福祉援助技術としての本来の姿ではないという極端な意見にぶつかると首を傾げるし、それこそ間違った考えであるといわざるを得ない。
バイスティックがこの原則を書いて初版を発刊したのは1957年である。日本ではその8年後に「ケースワークの原則〜より良き援助を与えるために」として田代不二男・村越芳男の両氏によって格調高い文章の訳書が発刊されている。1960〜1970年代の日本のワーカーは、この訳書によって、それを学び影響を受けたものと思える。
しかし僕らがその原則を学んだ訳書は、それとは異なり、内容も違ってきている。僕の手元にあるものは1996年が初版の尾崎新・福田俊子・原田和幸の3氏によって訳されたものであるが、副題からして「援助関係を形成する技法」と変わっている。
このことについて尾崎新氏は訳書の中で『学生時代にこの本を読んだときの感想として「より良き援助を与えるために」という副題は間違いではないかと考えました。援助とは与えるものではなくクライエントが自ら活用するもののはずだと考えました』と延べている。その考え方が副題の修正に繋がっているんだろう。
また訳書を書くに当たって原本のキーワードである Casework Relationship については「厳密に訳せばケースワーク関係とすべきでしょうが」と断った上で、臨床で日常的に使われている言葉として「ケースワークにおける援助関係」と変えた、と述べている。このように、初版本の内容と、その後に出された数々の訳書の内容は、それぞれ微妙に、あるいは箇所によっては大胆に意味が違っているのである。
つまり、それぞれの訳書で勉強した個人の理解の仕方も違う部分があるといえる点が一つ。それにも増して以下のような指摘がある。
原本の内容について尾崎氏は「バイスティックがこの本を書いた当時の時代背景を学習し、私自身の臨床体験を題材にして、バイスティックの論述に見られる内容の不明確さや不自然な点も洗い出し、議論もしました。これらの作業を通し、私はやはりこの本がケースワークの歴史の中で始めて援助関係という基本にこだわり援助関係の意義を具体的に提示し、さらに関係形成の技法を確立したという意味で大きな意義があることを確信しました。」と述べている。
しかし同時に氏は、この原則をそのまま臨床場面で使っても解決しない問題がある点について本書の「あとがき」の中で説明している。これは大事なことなので、一部抜粋して以下に紹介したい。
(一部僕がまとめる形で文章は修正していますが意味は変えていません。)
バイスティックはケースワーク臨床のもっとも重要な基礎が援助関係を形成することでありケースワークの技術とは援助関係を形成する技法であるという主張をその当時に行ったのです。おそらく当時のアメリカはクライエントの秘密を的確に守ることや、問題解決の方向やペースをクライエント自身が自分で選択することなどが重視されていなかったはずで、援助の基本が「熱意」や「善意」であるという考えが色濃く残っていた時代であったはずです。
その当時のバイスティックの主張は現在でも学ぶべき点は多いと思われます。しかしこの本は「古典」であるだけに我々が読む際に気をつけねばならない点があります。それは内容にも不自然・無理と思われる箇所がないわけではなく、われわれがバイスティックの原則を忠実に守ろうとするだけではかえって自分を抑制するだけの堅苦しい援助態度を身につけてしまって、結局それはクライエントにも伝わり堅苦しい援助関係しか作れないという事態を招く危険性があります。
我々はこの本がソーシャルワーカーの持っていた人権意識や倫理観が現在以上に磨かれていなかった時代に書かれたという時代背景を何度も確認しながら読み勧める必要性があります。バイスティックの書いた本は、あくまで原則・基礎を論ずるところにとどまっていることも忘れてはならないことです。
彼の主張だけを鵜呑みにして、それだけに頼っても様々な臨床場面に対応することは困難です。臨床は原則だけでは身動きがとれません。原則に加え、臨機応変で柔軟な思考や判断が求められます。また援助者の一人はそれぞれに自分に適した原則の生かし方を発見して開発していく必要もあります。
すなわちバイスティックは我々が援助関係を形成していく際の大まかな「羅針盤」を提示したに過ぎません。我々にとって大切なことはバイスティックの残した遺産を学んだ上で、一人ひとりが彼の議論を様々な形・方向で発展させることだといえます。
(引用要約以上)
つまりこの本を読んで形だけをまねても、臨床場面の相談援助がうまく展開できるというものではない、という理解も必要で、その原則の深い意味を考えながら、われわれに今求められている本質を探す日々の研鑽が不可欠であるということである。
少なくともこの原則を自分の都合のよいところだけつまみ食いのように使って言い訳にしてはならない。
必要な援助をしないことを「自己決定の原則」という言葉で屁理屈をこねてごまかしているのは、どこのどいつだ。
介護・福祉情報掲示板(表板)
(↓ランキング登録しています。クリックして投票にご協力をお願いします。)
人気blogランキングへ
にほんブログ村 介護ブログ
FC2 Blog Ranking
それだけこの原則が大事であるということだろうし、その原則を守る姿勢が援助関係を形成するために必要であるということについては、時代が変わった現代社会おいても同様であると考えられているということであろう。
僕もこのブログの中で、その原則に触れた話題を何回も書いており、その原則の意味や理解の仕方についても説明したりしている。(参照:この原則に触れた過去のブログ)
しかしこの原則がケースワークのすべてで、少しでもこの原則に則らない行為や考え方は間違っていて、社会福祉援助技術としての本来の姿ではないという極端な意見にぶつかると首を傾げるし、それこそ間違った考えであるといわざるを得ない。
バイスティックがこの原則を書いて初版を発刊したのは1957年である。日本ではその8年後に「ケースワークの原則〜より良き援助を与えるために」として田代不二男・村越芳男の両氏によって格調高い文章の訳書が発刊されている。1960〜1970年代の日本のワーカーは、この訳書によって、それを学び影響を受けたものと思える。
しかし僕らがその原則を学んだ訳書は、それとは異なり、内容も違ってきている。僕の手元にあるものは1996年が初版の尾崎新・福田俊子・原田和幸の3氏によって訳されたものであるが、副題からして「援助関係を形成する技法」と変わっている。
このことについて尾崎新氏は訳書の中で『学生時代にこの本を読んだときの感想として「より良き援助を与えるために」という副題は間違いではないかと考えました。援助とは与えるものではなくクライエントが自ら活用するもののはずだと考えました』と延べている。その考え方が副題の修正に繋がっているんだろう。
また訳書を書くに当たって原本のキーワードである Casework Relationship については「厳密に訳せばケースワーク関係とすべきでしょうが」と断った上で、臨床で日常的に使われている言葉として「ケースワークにおける援助関係」と変えた、と述べている。このように、初版本の内容と、その後に出された数々の訳書の内容は、それぞれ微妙に、あるいは箇所によっては大胆に意味が違っているのである。
つまり、それぞれの訳書で勉強した個人の理解の仕方も違う部分があるといえる点が一つ。それにも増して以下のような指摘がある。
原本の内容について尾崎氏は「バイスティックがこの本を書いた当時の時代背景を学習し、私自身の臨床体験を題材にして、バイスティックの論述に見られる内容の不明確さや不自然な点も洗い出し、議論もしました。これらの作業を通し、私はやはりこの本がケースワークの歴史の中で始めて援助関係という基本にこだわり援助関係の意義を具体的に提示し、さらに関係形成の技法を確立したという意味で大きな意義があることを確信しました。」と述べている。
しかし同時に氏は、この原則をそのまま臨床場面で使っても解決しない問題がある点について本書の「あとがき」の中で説明している。これは大事なことなので、一部抜粋して以下に紹介したい。
(一部僕がまとめる形で文章は修正していますが意味は変えていません。)
バイスティックはケースワーク臨床のもっとも重要な基礎が援助関係を形成することでありケースワークの技術とは援助関係を形成する技法であるという主張をその当時に行ったのです。おそらく当時のアメリカはクライエントの秘密を的確に守ることや、問題解決の方向やペースをクライエント自身が自分で選択することなどが重視されていなかったはずで、援助の基本が「熱意」や「善意」であるという考えが色濃く残っていた時代であったはずです。
その当時のバイスティックの主張は現在でも学ぶべき点は多いと思われます。しかしこの本は「古典」であるだけに我々が読む際に気をつけねばならない点があります。それは内容にも不自然・無理と思われる箇所がないわけではなく、われわれがバイスティックの原則を忠実に守ろうとするだけではかえって自分を抑制するだけの堅苦しい援助態度を身につけてしまって、結局それはクライエントにも伝わり堅苦しい援助関係しか作れないという事態を招く危険性があります。
我々はこの本がソーシャルワーカーの持っていた人権意識や倫理観が現在以上に磨かれていなかった時代に書かれたという時代背景を何度も確認しながら読み勧める必要性があります。バイスティックの書いた本は、あくまで原則・基礎を論ずるところにとどまっていることも忘れてはならないことです。
彼の主張だけを鵜呑みにして、それだけに頼っても様々な臨床場面に対応することは困難です。臨床は原則だけでは身動きがとれません。原則に加え、臨機応変で柔軟な思考や判断が求められます。また援助者の一人はそれぞれに自分に適した原則の生かし方を発見して開発していく必要もあります。
すなわちバイスティックは我々が援助関係を形成していく際の大まかな「羅針盤」を提示したに過ぎません。我々にとって大切なことはバイスティックの残した遺産を学んだ上で、一人ひとりが彼の議論を様々な形・方向で発展させることだといえます。
(引用要約以上)
つまりこの本を読んで形だけをまねても、臨床場面の相談援助がうまく展開できるというものではない、という理解も必要で、その原則の深い意味を考えながら、われわれに今求められている本質を探す日々の研鑽が不可欠であるということである。
少なくともこの原則を自分の都合のよいところだけつまみ食いのように使って言い訳にしてはならない。
必要な援助をしないことを「自己決定の原則」という言葉で屁理屈をこねてごまかしているのは、どこのどいつだ。
介護・福祉情報掲示板(表板)
(↓ランキング登録しています。クリックして投票にご協力をお願いします。)
人気blogランキングへ
にほんブログ村 介護ブログ
FC2 Blog Ranking
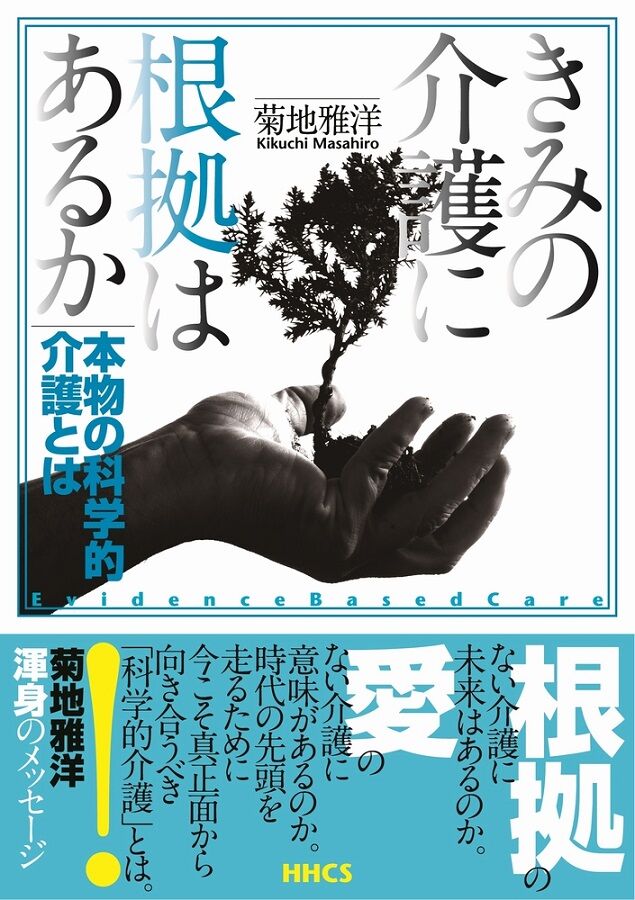
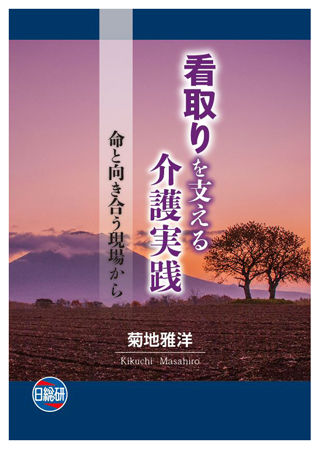

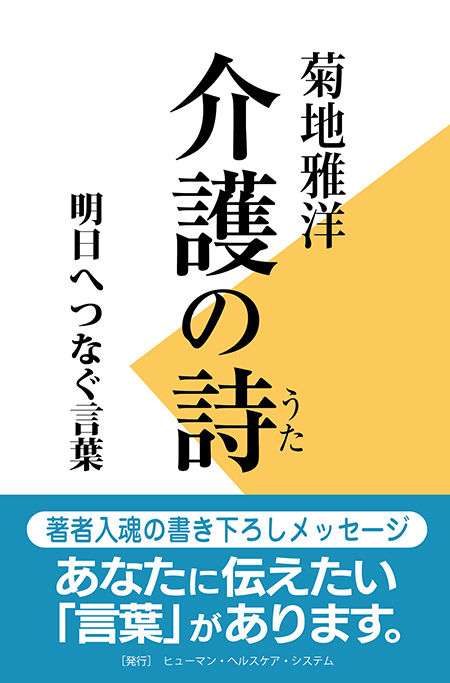
 感動の完結編。
感動の完結編。
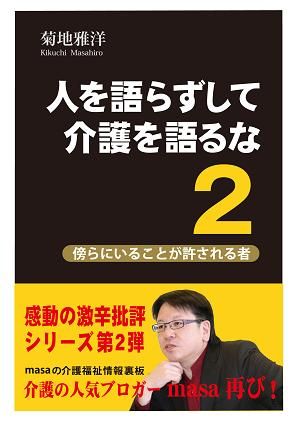
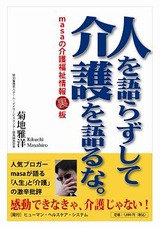
事例研究会で知り合った福祉職に話したら、「バイスッティクの7原則を読み直したら?」と言われ相談職の基本中の基本と・・・読み直してはみたものの・・・マスマス混乱。
本日のブログでその理由が理解できました。
「原則を探す日々」ではなく「本質を探す日々」を心掛けます。