在宅介護支援センターの主要な機能であった地域ケア会議。
地域における様々な「困難ケース」を多機関・多職種横断で総合的に支援するために話し合いが行われていた会議であるが、在宅介護支援センターがなくなり、地域包括支援センターに変わった以降、当市でその会議自体は市のシステムの中に残っているというのだが、実際にそれが行われて機能しているふうにはみえない。
特に問題と感じていることは、最近の地域の中で発見される困難ケースは高齢化が世帯丸ごと進行して、要介護者だけではなく、介護をすべきキーパーソンも自身の高齢化の問題を抱えて複雑な様相を呈している点である。
介護が不十分で悲惨な生活状況に置かれているのが90代の母親であるとして、その介護を担っている息子が独身の60代後半であるというケースがあるとする。
すると主訴が例えば十分な介護を受けていない母親の置かれた状況であるとしても、その原因は主たる支援者の加齢に伴う認知の悪化であったり、身体状況の変化であったりする場合がある。そして支援者自身が自分の状況変化に気付かずに、要介護者の悲惨な生活状況を作り出している現実がある。
こうしたケースでは、単に要介護者を保護するだけではなく、主たる支援者のケアも地域の中で継続的に必要になることが多い。しかしながら現状では、問題が表面化している要介護者を入院や施設入所に繋げて、とりあえず地域介護支援が終了してしまうというケースがある。
しかしこれでは早晩、地域の中で新たな問題として主たる支援者自身の生活問題が表面化してこよう。こうしたことを未然に防ぐ地域支援が求められているはずである。担当者と要介護者の保護先の関わりで終結すべきケースではないはずだ。しかしこれがなかなかうまく言っていない現状がある。
さらに精神的な障害を持つ子が、認知症の高齢者と同居していることで、どちらも問題の所在に気付かずに悲惨な状況で発見されるケースもある。
こうしたケースこそ地域包括支援センターが中心になって、関係諸機関が継続的に協議を重ね支援をしていくべきだろう。
当地域では制度改正後、地域包括支援センターが中心となって、関係諸機関や警察関係、町内会代表や民生委員代表が名を連ねて『高齢者支援連絡会』というあらたなチームが作られているが、1年以上協議を重ねているが「会議は踊る、されど進まず」で具体的な方向性が見えないまま惰性的に数だけ重ねられている。
支援連絡会で行おうとしている事業と社協の地域福祉実践計画事業とが区分できず両者が別々に同じようなことをしているという指摘もある。そもそも当市の場合、地域包括支援センターを統括する担当課をはじめ、市の福祉事業の担当課と、市社会福祉協議会との協力・連携体制がほとんど構築されていないのが問題だろう。
高齢者支援連絡会のメンバーの中には、社協事業の推進会議メンバーも含まれているが、どっちに力を注ぐかという視点からしか議論の方向が見えない人もいる。認知症サポーター養成講座を主催するにしても、その意味を理解せず、サポーターをせっかく養成するんなら、サポーターに何か役割を担ってもらわなければ意味がないと考え、会議が先に進まなかった経験もある。どうしようもない。
高齢者支援連絡会は、社協が行っている地域のニーズ調査やモデル事業は一度、この会議の機能からはずして、専門家集団として、地域包括支援センターの職員を中心に、実際に地域で発見された困難ケースを具体的、継続的に支援する「地域ケア会議」の機能を中心にすえて、その構成メンバーも一度白紙に戻して、再度洗いなおして再編成した方がよいだろう。
開催しているだけの会議、ただの調査機関、モデル事業をとりあえず行う機関では意味がないのである。
地域の中で隠されたネグレクトをはじめとした虐待や、世帯総ぐるみで世帯自身が気付いていない生活障害に適切にかつ迅速に対応できるシステムが高齢者支援連絡会の向かう方向ではないのだろうか。
今月開催された連絡会では、そのような方向から意見を述べたが、どれだけ伝わったことか・・・。モデル事業を繰り返す影で、本当に困っている人が救われない現状が地域の奥深くで進行しているとしたら何のためのモデル事業なんだろう。本当に困っている人に手を差し伸べるシステムは一刻も早く構築するというスピードが必要だし、この連絡会は実行部隊でなければ意味がない。
地域の介護問題の最終的なセーフティネットにならなくてどうするのだろうか。
介護・福祉情報掲示板(表板)
(↓ランキング登録しています。クリックして投票にご協力をお願いします。)
人気blogランキングへ
にほんブログ村 介護ブログ
FC2 Blog Ranking
地域における様々な「困難ケース」を多機関・多職種横断で総合的に支援するために話し合いが行われていた会議であるが、在宅介護支援センターがなくなり、地域包括支援センターに変わった以降、当市でその会議自体は市のシステムの中に残っているというのだが、実際にそれが行われて機能しているふうにはみえない。
特に問題と感じていることは、最近の地域の中で発見される困難ケースは高齢化が世帯丸ごと進行して、要介護者だけではなく、介護をすべきキーパーソンも自身の高齢化の問題を抱えて複雑な様相を呈している点である。
介護が不十分で悲惨な生活状況に置かれているのが90代の母親であるとして、その介護を担っている息子が独身の60代後半であるというケースがあるとする。
すると主訴が例えば十分な介護を受けていない母親の置かれた状況であるとしても、その原因は主たる支援者の加齢に伴う認知の悪化であったり、身体状況の変化であったりする場合がある。そして支援者自身が自分の状況変化に気付かずに、要介護者の悲惨な生活状況を作り出している現実がある。
こうしたケースでは、単に要介護者を保護するだけではなく、主たる支援者のケアも地域の中で継続的に必要になることが多い。しかしながら現状では、問題が表面化している要介護者を入院や施設入所に繋げて、とりあえず地域介護支援が終了してしまうというケースがある。
しかしこれでは早晩、地域の中で新たな問題として主たる支援者自身の生活問題が表面化してこよう。こうしたことを未然に防ぐ地域支援が求められているはずである。担当者と要介護者の保護先の関わりで終結すべきケースではないはずだ。しかしこれがなかなかうまく言っていない現状がある。
さらに精神的な障害を持つ子が、認知症の高齢者と同居していることで、どちらも問題の所在に気付かずに悲惨な状況で発見されるケースもある。
こうしたケースこそ地域包括支援センターが中心になって、関係諸機関が継続的に協議を重ね支援をしていくべきだろう。
当地域では制度改正後、地域包括支援センターが中心となって、関係諸機関や警察関係、町内会代表や民生委員代表が名を連ねて『高齢者支援連絡会』というあらたなチームが作られているが、1年以上協議を重ねているが「会議は踊る、されど進まず」で具体的な方向性が見えないまま惰性的に数だけ重ねられている。
支援連絡会で行おうとしている事業と社協の地域福祉実践計画事業とが区分できず両者が別々に同じようなことをしているという指摘もある。そもそも当市の場合、地域包括支援センターを統括する担当課をはじめ、市の福祉事業の担当課と、市社会福祉協議会との協力・連携体制がほとんど構築されていないのが問題だろう。
高齢者支援連絡会のメンバーの中には、社協事業の推進会議メンバーも含まれているが、どっちに力を注ぐかという視点からしか議論の方向が見えない人もいる。認知症サポーター養成講座を主催するにしても、その意味を理解せず、サポーターをせっかく養成するんなら、サポーターに何か役割を担ってもらわなければ意味がないと考え、会議が先に進まなかった経験もある。どうしようもない。
高齢者支援連絡会は、社協が行っている地域のニーズ調査やモデル事業は一度、この会議の機能からはずして、専門家集団として、地域包括支援センターの職員を中心に、実際に地域で発見された困難ケースを具体的、継続的に支援する「地域ケア会議」の機能を中心にすえて、その構成メンバーも一度白紙に戻して、再度洗いなおして再編成した方がよいだろう。
開催しているだけの会議、ただの調査機関、モデル事業をとりあえず行う機関では意味がないのである。
地域の中で隠されたネグレクトをはじめとした虐待や、世帯総ぐるみで世帯自身が気付いていない生活障害に適切にかつ迅速に対応できるシステムが高齢者支援連絡会の向かう方向ではないのだろうか。
今月開催された連絡会では、そのような方向から意見を述べたが、どれだけ伝わったことか・・・。モデル事業を繰り返す影で、本当に困っている人が救われない現状が地域の奥深くで進行しているとしたら何のためのモデル事業なんだろう。本当に困っている人に手を差し伸べるシステムは一刻も早く構築するというスピードが必要だし、この連絡会は実行部隊でなければ意味がない。
地域の介護問題の最終的なセーフティネットにならなくてどうするのだろうか。
介護・福祉情報掲示板(表板)
(↓ランキング登録しています。クリックして投票にご協力をお願いします。)
人気blogランキングへ
にほんブログ村 介護ブログ
FC2 Blog Ranking
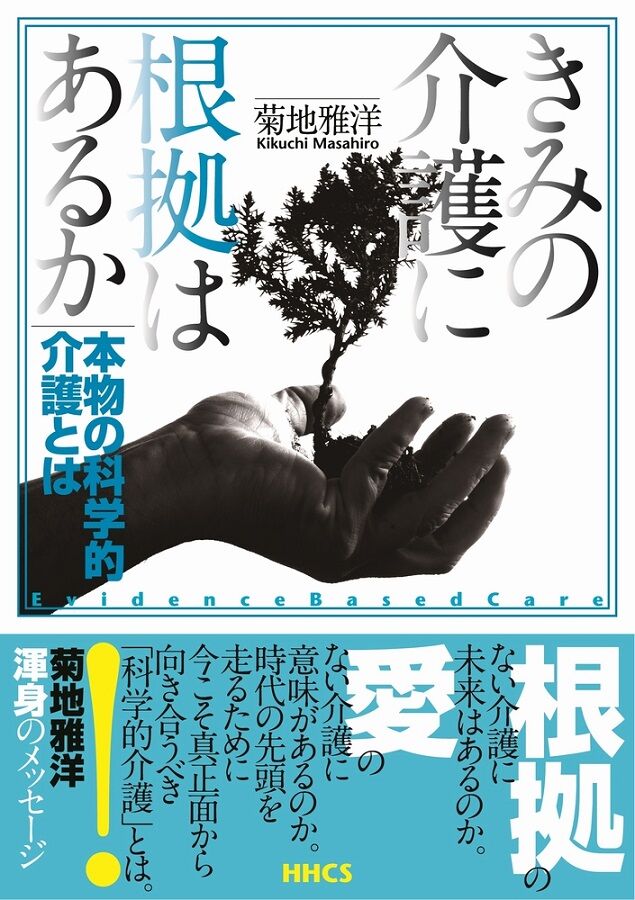
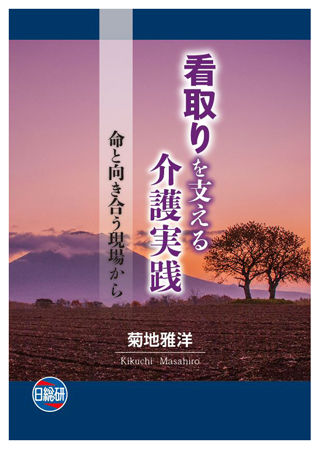

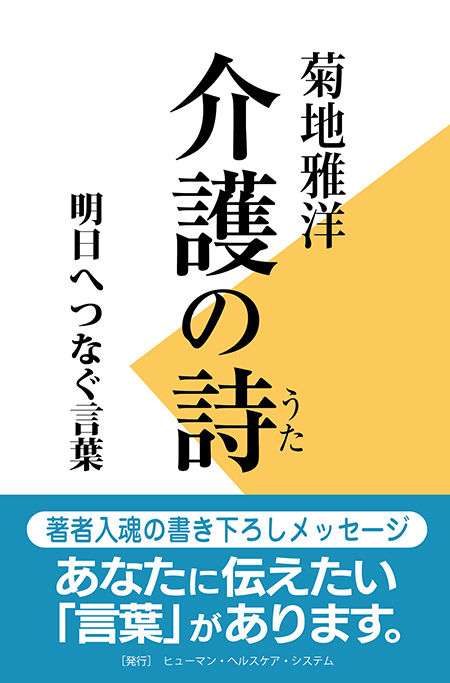
 感動の完結編。
感動の完結編。
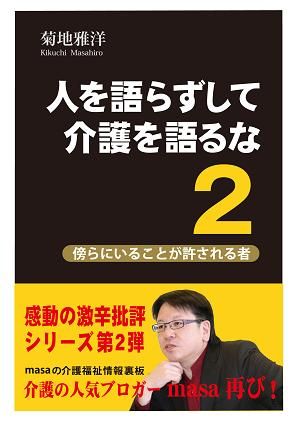
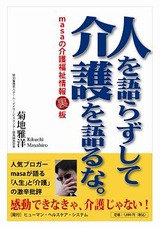
ご指摘の通り。
いつにもまして現場で真摯に立ち向かう人にして発言できることですね。
これから
もっと多くの地域で
同様の課題がでてくることが
容易に想定されます。
と
ここまでは私もいえるのですが
具体の場では
もっと
汗が流されないと
前進はありませんね。