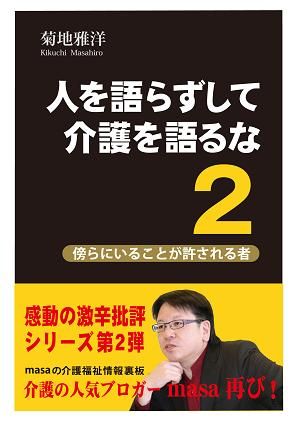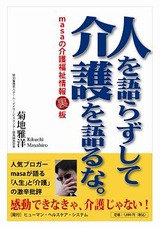高齢要介護者の介護予防において大切なのは、実は、機能を良くしてから生活改善を図るという視点でなく、生活を良くする取り組みの中で、利用者の喜びや意欲が生まれ、そのことが機能改善や維持に繋がるという視点である。
4月から始まる新予防給付にこの視点が欠けてはいないだろうか?
それはさておき、具体的な話に戻そう。
現在様々な場面で、筋力トレーニングを含めた機能訓練メニューが重視されているが、これは果たして生活改善、機能維持に最も効果があるメニューになり得るのであろうか。
少なくとも昨日のブログで述べてきた状況や視点からは、我々の施設の中で、それは機能維持や生活改善に繋がるような主要なメニューにならないと考える。
もちろん機能訓練自体を否定するものではないが、まず機能訓練ありき、ではなく、個々の利用者の能力が生かされる暮らしを作る中で利用者は自ら持つ能力や機能を生かすことができ、生き生きとした生活の中でこそ、様々な意欲が持てるのである。
逆に、訓練によって機能を維持しないと、良い暮らしが実現できないという立場に立つとしたら、そうした考えが重荷にならないで数十年の生活を継続できる強い人間はそう多くないであろう。
大事なことは、機能訓練というメニューでさえも、気楽に楽しく、生活と結びついた状況の中でごく自然に行われる、ということである。なぜなら特養は10年20年〜というスパンでの「暮らし」の場なのであり、嫌なこと、痛いこと、面倒なこと、は続かないし、効果を生まないのである。
具体的に言えば、当施設には専任のPTやOTはおらず、訓練指導員は看護師が兼務し、機能訓練加算の算定は行っていない。
その中で例えばボールゲームや風船バレーなどのいわゆる遊びリテーションや療育音楽、回想法などのグループワークを選択メニューとして日課活動に取り入れているが、要は「心が動けば体も動く」という具体策が展開されることが必要なのであり、逆に言えば「心が動かなければ体も動かない」ということである。
今日、施設のケアの提供体制の「集団的処遇」が槍玉に上がり、脱集団処遇と個人の生活行為を中心とした個別ケアの視点が重視されケアの方法が「プログラム化」から「生活支援型」に転換されつつあるが、グループワークが一律、個別性や主体性を軽視したプログラムと考えるのは間違いであり、それに選択性があり、個人のニーズにマッチして動機付けや、意欲の向上につながるのであれば自立支援や生活改善に有効なツールであることに変わりはないし、廃用に対する対策にとどまらず、認知症の方への意欲引き出しや生活改善にも繋がるツールになり得るのである。(明日に続く)
介護・福祉情報掲示板(表板)
4月から始まる新予防給付にこの視点が欠けてはいないだろうか?
それはさておき、具体的な話に戻そう。
現在様々な場面で、筋力トレーニングを含めた機能訓練メニューが重視されているが、これは果たして生活改善、機能維持に最も効果があるメニューになり得るのであろうか。
少なくとも昨日のブログで述べてきた状況や視点からは、我々の施設の中で、それは機能維持や生活改善に繋がるような主要なメニューにならないと考える。
もちろん機能訓練自体を否定するものではないが、まず機能訓練ありき、ではなく、個々の利用者の能力が生かされる暮らしを作る中で利用者は自ら持つ能力や機能を生かすことができ、生き生きとした生活の中でこそ、様々な意欲が持てるのである。
逆に、訓練によって機能を維持しないと、良い暮らしが実現できないという立場に立つとしたら、そうした考えが重荷にならないで数十年の生活を継続できる強い人間はそう多くないであろう。
大事なことは、機能訓練というメニューでさえも、気楽に楽しく、生活と結びついた状況の中でごく自然に行われる、ということである。なぜなら特養は10年20年〜というスパンでの「暮らし」の場なのであり、嫌なこと、痛いこと、面倒なこと、は続かないし、効果を生まないのである。
具体的に言えば、当施設には専任のPTやOTはおらず、訓練指導員は看護師が兼務し、機能訓練加算の算定は行っていない。
その中で例えばボールゲームや風船バレーなどのいわゆる遊びリテーションや療育音楽、回想法などのグループワークを選択メニューとして日課活動に取り入れているが、要は「心が動けば体も動く」という具体策が展開されることが必要なのであり、逆に言えば「心が動かなければ体も動かない」ということである。
今日、施設のケアの提供体制の「集団的処遇」が槍玉に上がり、脱集団処遇と個人の生活行為を中心とした個別ケアの視点が重視されケアの方法が「プログラム化」から「生活支援型」に転換されつつあるが、グループワークが一律、個別性や主体性を軽視したプログラムと考えるのは間違いであり、それに選択性があり、個人のニーズにマッチして動機付けや、意欲の向上につながるのであれば自立支援や生活改善に有効なツールであることに変わりはないし、廃用に対する対策にとどまらず、認知症の方への意欲引き出しや生活改善にも繋がるツールになり得るのである。(明日に続く)
介護・福祉情報掲示板(表板)
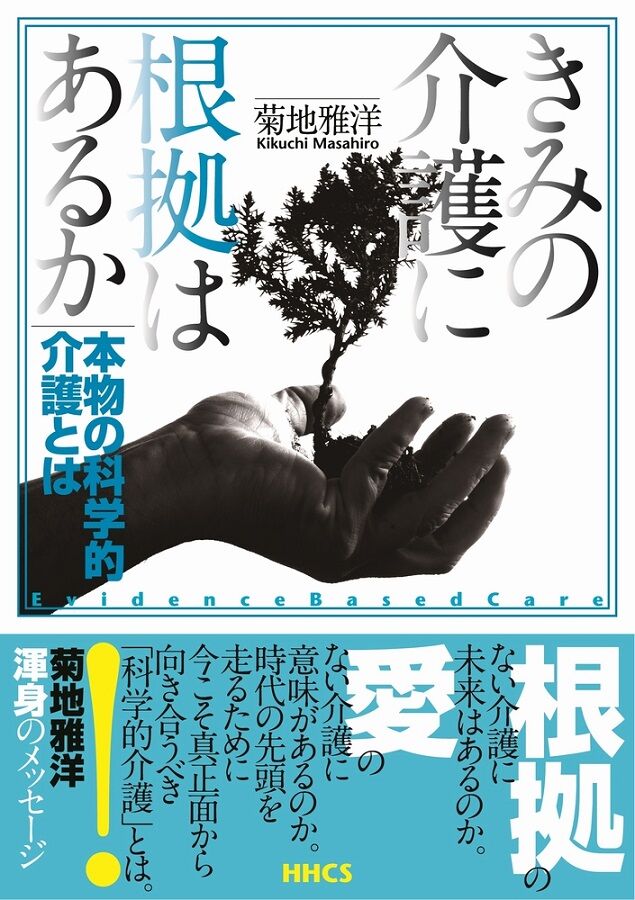
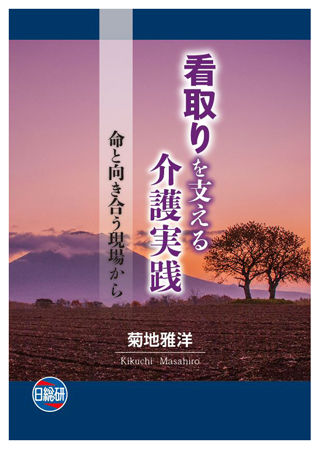

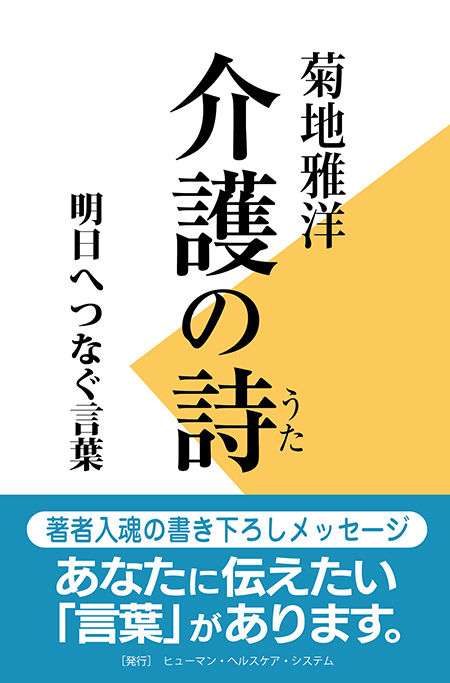
 感動の完結編。
感動の完結編。